残業はほぼなし 子育て支援や奨学金制度も充実 認知症専門の病院|医療法人社団 純正会 青梅東部病院
- 更新日

「青梅東部病院」は、東京都青梅市にある認知症専門の病院です。青梅市内の景色や奥多摩の山々を眺めることができる、緑豊かな環境が魅力です。フランス発の認知症ケア技法や、患者様が希望する外出先に出かけるプログラムなど、患者様のための様々な取り組みをしています。
東京都青梅市で認知症患者様1人1人の状態に合った医療サービスを提供している「青梅東部病院」。残業はほぼなく、有休取得も積極的に促すなど、ワークライフバランスを大切にしている職場です。看護学校に進学する際の学費補助など、スキルアップ支援も充実しています。
目次
フランス発の認知症ケア技法も取り入れた、認知症専門の病院

―青梅東部病院は、どのような病院ですか。
当院は東京都青梅市にある認知症専門の病院です。病棟は3病棟に分かれており、階ごとに60名ずつ患者様を受け入れています。病床数は180床です。患者様に対する職員の割合は、看護師が20対1、看護補助者が25対1です。
当院の特徴として、言語聴覚士がいることが挙げられます。高齢の患者様が今後も増えていく中で、嚥下に対するアプローチを進め、誤嚥性肺炎を予防する体制が整っています。
また、認知症の個別リハビリテーションも行っています。1人あたり約20分間かけて病院まわりを散歩したり、野菜の種まきや収穫を行ったりしています。
作業療法士による集団リハビリも実施しており、患者様を寝たきりにさせないというモットーを大切にしています。
フランス発の認知症ケア技法である、ユマニチュードⓇも取り入れています。「見る」「触れる」「話す」「立つ」という4つの柱を基本とし、患者様に声掛けをしたり、目線を合わせたり、触れたりすることで、患者様が不穏状態に陥っている時に安心させる技法です。入院したての患者様は特に、慣れない環境で不穏状態が強く出る場合があります。また認知症の特性上、入院中に急にうつ病の症状が出ることもあります。そういう時にユマニチュードⓇの技法を使い、患者様の不穏を取り除いています。
患者様の希望をかなえるプログラムもあります。「野球観戦に行きたい」とおっしゃっていた患者様と、近くの球場にプロ野球観戦に行ったこともありました。外出がしたくても家族だけでは不安という方のために、ご家族と一緒に外出をすることもあります。中には、秩父に外出し、三峯神社にお参りしたり、秩父太鼓や名物のくるみそばを召し上がっていただいたりして、ご家族と有意義な1日を過ごした方もいらっしゃいました。
慰問もあり、秩父の学校の方に和太鼓を披露していただく機会があります。また地域の小さなお子様から大学生まで在籍しているバトンクラブが年に1回慰問に来られますが、患者様にとても喜ばれます。
他の精神科ではできないようなことをできる限りしたいという思いがあり、職員からのアイデアは医師の許可があれば基本的には実現しています。
―青梅東部病院の看護職の具体的なお仕事内容をご紹介いただけますか。
日勤帯に関しては、朝は朝食の介助から始まり、おむつ交換と入浴を行います。その後、お昼の配膳をして、食事介助をします。その後は排泄の支度ですね。当院ではお部屋のベッドでおむつ交換をしているので、いったんお部屋に戻っていただきます。その後は、集団リハビリのためにまたホールに出ていただきます。そこでおやつとお茶を出すのが看護助手の仕事です。
看護師は朝のバイタルチェックを行い、必要であれば医師に報告して指示を仰ぎ、処置を行います。当院では、看護師は看護助手と一緒におむつ交換も入浴も仕事の一環として行っています。
残業はほぼなし 男性も含め育休も取りやすい
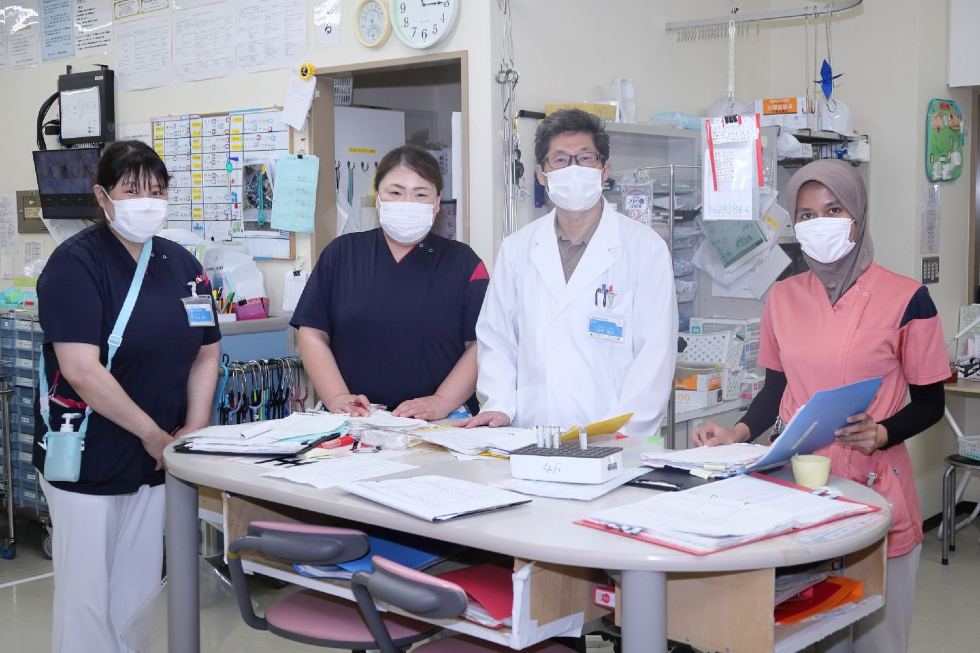
―スタッフの皆さんは、どんなことを大切にしてお仕事にあたっていますか。
認知症の患者様だと、言ったことが理解できない方も多くいらっしゃいますが、目線を合わせたり、優しい声掛けをしたりと、患者様に働きかけることを大切にしています。
―青梅東部病院で働くやりがいをどんな場面で感じますか。
今まで拒食状態だった患者様がユマニチュードⓇを介して食事をとるようになるなど、目に見えて分かる成果が出てくることがやりがいにつながっています。
―職場の雰囲気について教えてください。
看護師と看護助手は全部で100名ほどいます。看護師の男女比は、女性が7割に対して、男性が3割程度です。年齢層は幅広く、20代から60代の職員までいます。
当院ではレクリエーションに力を入れていますが、その際も職員間のコミュニケーションがよく取れていると思います。
また年に何回か、職員に向けて豚汁などの食事を作って振る舞う取り組みをしています。
先日は初めての試みでクレープのキッチンカーを呼びました。夜勤明けの職員も購入できるよう朝から夕方まで来ていただき、楽しい雰囲気でした。
―普段、仕事上のコミュニケーションはどのように取っていますか。
コミュニケーションの基本は挨拶だと思います。当院には特定技能実習生の看護助手がいますが、日本語が伝わりづらいこともあります。そのため、できる限り分かりやすく話したり、しっかりとヒアリングしたりして、コミュニケーションを取るよう心がけています。
お互いに相手のことを思い合って、されて嫌なことはしないといった基本を大切にしています。
―ワークライフバランス面のPRポイントについてうかがえますか。
残業はほぼなく、皆定時で上がっています。特に送迎バスを利用しているスタッフは、バスに乗り遅れると帰れなくなってしまうので、優先的に帰ってもらっています。
管理職に関してはこの限りではないですが、一般職に関しては17時になったら全員帰っていきます。
有休についても、できる限り取得を促して、取りやすい状況を作っています。
育児や介護との両立に関しても、しっかりサポートしています。当院では、これまで男性職員3名が育休を取得しています。介護をする職員に向けても、できる限り介護休暇を取れる制度を作っている最中です。
―DXなど業務改善の取り組みはしていますか。
来年の秋頃に向けて、電子カルテの導入を準備しています。
また病棟クラークが病棟間の用事を全て担うようになったため、今まで複数のフロアを行き来していた看護師の負担がかなり軽減されました。
保育園や学童の費用補助、病気時の収入補填も

―待遇や福利厚生面でのPRポイントはありますか。
賞与・昇給については、年功序列という考え方は一切なく、あらかじめ設定した目標の到達度に基づいて定められています。
長く勤めていても、接遇があまり良くなかったり、患者様から繰り返しクレームが来たりする場合があれば、指導もしますし、評価にも反映します。厳しいとは思いますが、しっかり働いている職員を評価しないと全体にとっての不信感にもつながりかねないという考えのもと、公正に評価をしています。
福利厚生では、保育園と学童保育の費用補助をしています。保育園は常勤の方であれば全額支給し、学童保育に関しても常勤の方に全額を補助しています。
怪我や病気をした時の収入補填もあります。病院側が全額負担しているため、個人の負担は一切ありません。
例えば治療が長期間にわたる病気にかかり、一定期間を超えると、傷病手当と当院独自の保険金を合わせて、手取りに近い額の保障を受けることができます。60歳までという年齢制限はありますが、安心だと思います。
また病院として千葉にリゾートマンションを1部屋持っており、職員が利用できます。職員のクラブ活動も盛んで、フットサル部や写真部、ランナーズクラブがあり、大会に出る際の費用負担もしています。
―スキルアップ支援はありますか。
今年度から教育体制を強化しています。転職してきた職員は急性期の経験があることも多く、当院でのスキルアップは精神科に特化した部分が主になります。
そこで、レベルに応じて学べるeラーニングを導入しました。慢性期の療養型病棟とは違い、当院で看護師が患者様にできることは点滴や経管栄養など基本の部分になります。そのため、技術面よりは、知識面を強化しています。
奨学金制度もあり、例えば准看護師が看護師を目指したいのであれば、資質を見極めた上で、学費を全額補助して進学を支援します。
また、看護学校に進学したい看護助手に関しても、看護師長や看護部長たちが資質を見極めて推薦を出し、それが通れば受験に進みます。
進学先は看護学校か准看護学校の2つに分かれますが、多くの場合は准看護学校で資格免許を取ってから、看護師国家試験を受験して看護師になる道をたどります。5年程度の時間がかかりますが、9割ほどは卒業して国家資格を取れています。
研修も大事にしています。最初の研修では、各セクションを回ってオリエンテーションを経験し、看護部の場合は目標を立て、その目標に向かって数ヶ月単位でこまめに成長を見ていく仕組みになっています。
―キャリアパスについて教えてください。
実力がありリーダーシップが取れる職員に関しては、主任から始まって師長までキャリアアップできます。
実際に今の看護師長たちは、当院のサポートのもとで学校を卒業した職員です。リーダーシップのある人にはどんどん成長して次世代のリーダーとなってほしいと思っています。
―求める人材像について教えてください。
コミュニケーション能力が高い方に来ていただきたいですね。人同士でうまく付き合えてこそ、いいケアができると思っています。
経験の面では、できれば精神科の経験や、認知症の患者様をお世話した経験がある方を求めています。
例えば急性期や慢性期病棟で経験を積み、その先のステップとして、今後の社会のニーズに応えるために認知症の専門知識をつけたい方などに来ていただきたいと思います。
―入職を考えている方へのメッセージをお願いします。
患者様にも職員にも、この病院で良かったと思ってもらえるような病院づくりをしていきたいと考えています。
そのために、職員1人1人の意見をしっかりと吸い上げ、反映させていくつもりです。



