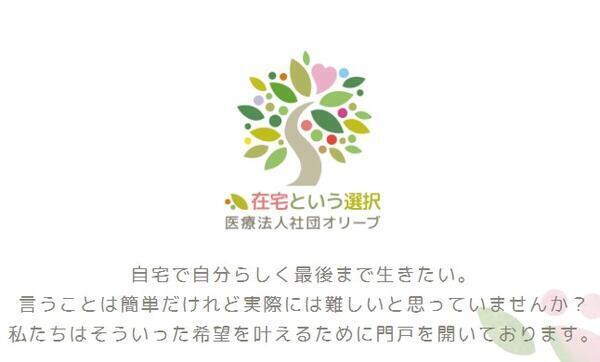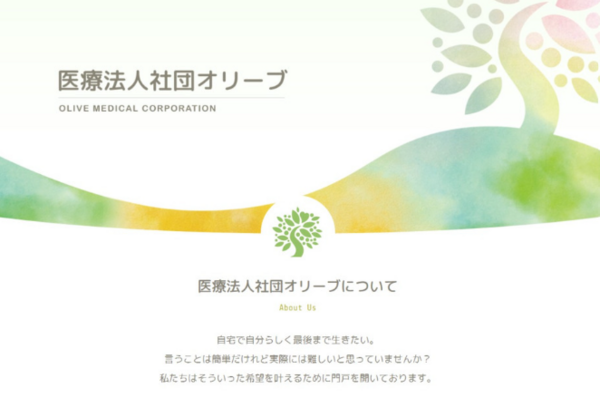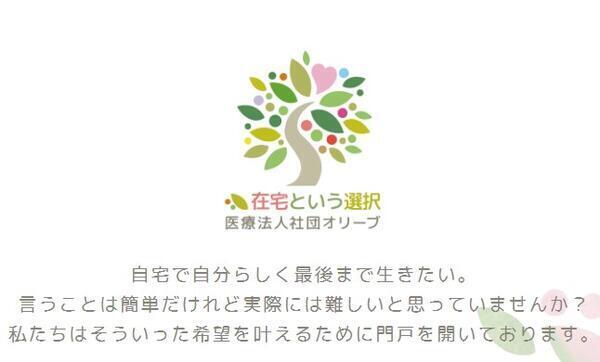住み慣れた環境で、その人らしい生活を。柔軟な働き方と職種間連携のしやすさが魅力の訪問看護ステーション|株式会社Olea オリーブ訪問看護リハビリステーション
- 更新日

株式会社Oleaは、東京都内で「オリーブ訪問看護リハビリステーション墨田」「オリーブ訪問看護リハビリステーション江東」という2拠点の訪問看護ステーションを運営しています。サービスを提供するのは、江東区、墨田区、台東区、中央区がメインです。がんの緩和ケアや終末期医療をはじめ、さまざまな症例の利用者の在宅生活を支えています。
連携施設の医療法人が運営するクリニックや居宅介護支援事業所などが併設されているため、他職種との連携が取りやすいのが大きな特徴。この他にも、訪問先への直行・直帰を選択可能とするなど、柔軟な働き方が選べるのもうれしいポイントです。
今回は、オリーブ訪問看護リハビリステーションで統括とリハビリ部長を務める浅野さんにインタビュー。働きやすい環境整備のために力を入れていることなどについてお話をお聞きしました。
目次
1.連携クリニックなどがワンフロアに

-ステーションではどのような職種の方が働いていますか?
浅野さん:
看護師は25人、リハビリ職は理学療法士と作業療法士、言語聴覚士が合計で19人、事務スタッフが4人働いています。
特徴的なのが、連携施設であるクリニックや居宅介護支援事業所なども同じ施設内に併設されている点です。施設全体で見ると、100人ほどのスタッフがいますよ。
-職場の雰囲気はいかがでしょうか?
浅野さん:
他の訪問看護ステーションに比べても、コミュニケーションが取りやすい環境だと感じますね。医師や薬剤師、ソーシャルワーカー、ケアマネージャーなどもワンフロアに集まっているため、専門外のことでも相談や質問しに行きやすいのは大きなメリットです。この点も含め、良好な人間関係を築きやすいのではないでしょうか。
-訪問時のお仕事の流れを簡単に教えてください。
浅野さん:
1日の訪問件数は、看護師・リハビリ職ともに5~6件が一般的ですね。決められたスケジュールに沿って、自転車や原付、バイクなどで移動します。ちなみに私たちリハビリ職の場合、利用者さんは担当制のため、訪問先はよく慣れた患者さんの自宅であることがほとんどです。
1件当たりの訪問時間は、リハビリ職の場合60分ほど。看護師の場合は利用者さんの状態しだいで、30~90分ほどと幅があります。特に、当ステーションでは終末期ケアの受け入れも多いため、そのような利用者さんに対してはじっくりと時間をかけて関わっていきます。
直行・直帰が選択できるのもポイントです。毎朝必ず全員が顔を合わせるわけではありませんが、iPadが1人1台貸与されるため、チャットツールや電子カルテを通して情報共有や連絡が可能です。もちろん、直接相談したいことがあれば事務所に来てもいいですし、チームカンファレンスの時間も設けています。
クリニックが連携施設となっていることで医師とスピーディーに連携が取れるため、発熱のために点滴が必要な場合など、緊急性の高い利用者さんへの対応がしやすいことも特徴といえるかもしれません。そうした場合に備えて、看護師のスタッフは通常よりも多めに輸液セットを持ち歩いているようです。
2.在宅医療は難しさの中にやりがいがある

-訪問看護や訪問リハビリといった在宅医療ならではのやりがいや魅力、注意すべき点について教えてください。
浅野さん:
どこのステーションでも共通することだとは思いますが、在宅医療は利用者さんご本人の生活にスポットを当てて介入していくものなので、そこが一番のおもしろさややりがいだと感じます。
特に終末期の利用者さんの場合、その方の人生を締めくくる最期の時間に寄り添い、少しでも安らかに過ごしてもらうお手伝いをするのが私たちの役目。ご家族へのケアも含め、どう向き合っていくかは難しい部分もありますが、その分達成感も大きいです。
一方で、訪問時は基本的に自分1人のため、さまざまなことを自身で判断しなければならない大変さもあります。病院だとナースコールを押せば看護師や医師が駆けつけてくれますが、訪問ではそうはいきません。どのタイミングで医師の指示を仰ぐかを含め、リスク管理が非常に重要になります。
病院に入院する場合は医療側のテリトリーに患者さんが入る形となるので、「適切なケアやリハビリのために必要だからこうしてほしい」という説明が通りやすいんですよね。しかし在宅だと、そう簡単にいかない場合も多いです。利用者さんの意向に寄り添いつつも、どのような声掛けをすればいいか工夫や注意する必要があると思います。
病院と自宅では環境が全く違うので、利用者さんが退院して在宅に戻った場合は想定外の事態もたくさん起こります。例えば、病院では歩行器を使えば歩けていたけれど自宅には十分なスペースがないなど、病院でやっていたことをそのまま在宅で反映できるとは限りません。逆に、「このまま退院して大丈夫なのか?」と心配されていた患者さんが、自宅では思いのほか動けることもあるんですよ。
いずれにせよ、一人ひとりの状態や環境に合わせたケアやリハビリの結果、利用者さんが良くなっていく姿を見るのは、難しさがあるからこそのやりがいも大きいですね。
3.直行・直帰が選択可能。未経験でも安心のフォロー体制も

-スタッフの働きやすさのために、力を入れていることや工夫していることはありますか?
浅野さん:
先ほどもご説明しましたが、当ステーションでは直行・直帰が選べるシステムを採用しています。事務作業や記録業務などは、貸与しているiPadで場所を問わずこなせるため、より柔軟な働き方ができるのではないでしょうか。
フロア内の職種間連携についても、上長が進んで他職種にアプローチすることで、全員が気兼ねなくコミュニケーションを取れるような雰囲気を作っています。
また、当ステーションではスタッフをいくつかのチームに分け、チームごとにカンファレンスを毎週開催しています。カンファレンスには看護師やリハビリ職はもちろん、医師やソーシャルワーカーなども出席し、利用者さんの情報を共有。個々のスタッフだけでなく、チーム全体でも利用者さんの状態を把握しつつ、不安点や疑問点の解消につなげます。
日ごろの頑張りがしっかりと給与に反映されるよう、基本給に加算されるインセンティブが充実しているのも特徴です。看護師の場合、月単位で1日当たりの訪問数が4件以上の場合はインセンティブを付与。オンコール当番手当も、平日か土日祝かなどの状況に応じて幅広く設定しています。リハビリ職の場合、1日当たり12単位を超えるとインセンティブが発生します。
突発的な休みに関しては、訪問先への移動が必要という都合上、病院に比べると他のスタッフへの急な代行依頼は難しい面があるかもしれません。そこで、上長が緊急時に備えてスケジュールを空けておくなど、各チームでフォローし合う体制を整えています。
この他、細かいことですが、事務所にはフリードリンクやフリー軽食も用意されていますよ。
-訪問業務が未経験のスタッフに対しては、どのようなフォロー体制がありますか? また、スタッフのスキルアップやキャリアアップをサポートする取り組みがあれば教えてください。
浅野さん:
基本的には所属するチームメンバーがフォローする体制を取っています。初めは先輩スタッフが同行し、習熟度合いに応じて徐々に1人での訪問に切り替えていく流れです。チームカンファレンスも定期的に開いているため、相談や質問がしやすい環境が整っていると考えています。
医師や薬剤師のような他職種との連携がしやすい点は、知識が得やすいという面でスキルアップにもつながっていますね。かといって他職種に頼りきりにするのではなく、チーム全体でもうまくフォローできるような体制づくりを心がけています。
この他、外部の研修に参加する際は、申請して許可を得れば参加費を補助する制度も用意しています。
4.自分の家族を任せられるようなステーションを目指して

-今後、地域の中でどのようなステーションを目指していらっしゃいますか?
浅野さん:
当ステーションでは、「住み慣れた環境でその人らしく、またご家族も幸せな生活を送れるように心に寄り添った看護・リハビリを提供します」「働く仲間とその家族に感謝し、ともに学び・助け合い知識の向上を図ります」「地域に根差した、愛し愛されるステーションを目指します」という3つの理念を掲げています。
この理念の下、自分の家族を任せられるような訪問看護ステーションを目指し、スタッフ一丸となって努力していく所存です。
-どんな人と一緒に働きたいですか? または、どんな人が活躍できる職場ですか?
浅野さん:
どこの訪問看護ステーションでも共通する点ですが、やはり患者さんの立場に立って考えられることが大切だと思います。訪問時は単独で行動することになるため、先輩や上長が常にそばにいられるわけではありません。そのような状況でも、しっかりと患者さん目線で自分のすべきことを考え、行動に移せる力を持った人と一緒に働けるとうれしいですね。
在宅医療の経験も問いません。当ステーションでは、訪問業務は全く未経験だったスタッフも多数活躍しています。もちろん、経験がない分初めは苦労する部分も多いと思いますが、しっかりと周囲がフォローする環境が整っているため、ご安心ください。
-最後に、記事を読んでいる求職者の方にメッセージをお願いします。
浅野さん:
当ステーションの魅力や他との違いは、実際に見ていただくのが一番だと考えています。興味を持ってくださった方は、まずは一度見学に来て、雰囲気を感じてもらえたらうれしいです。ぜひ、お気軽にご連絡ください。