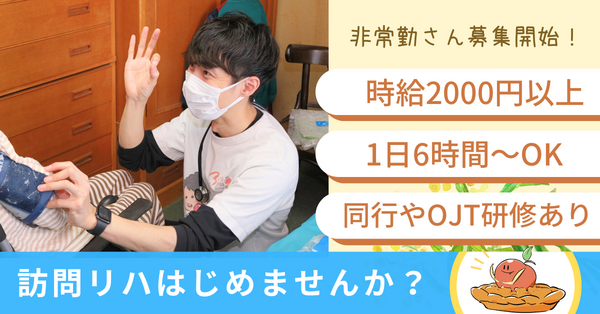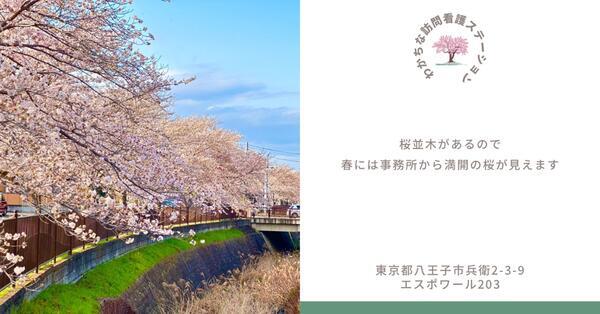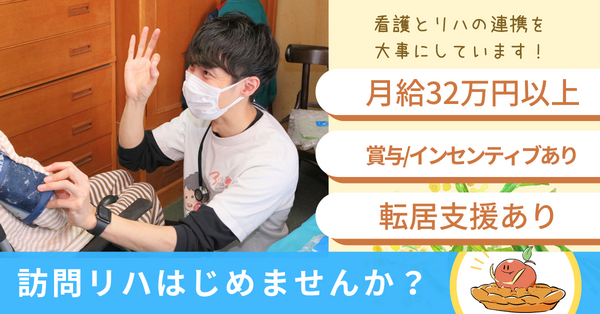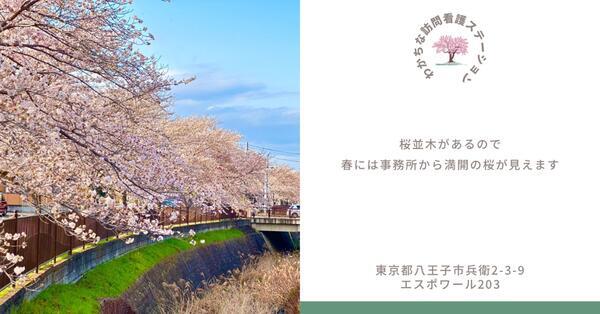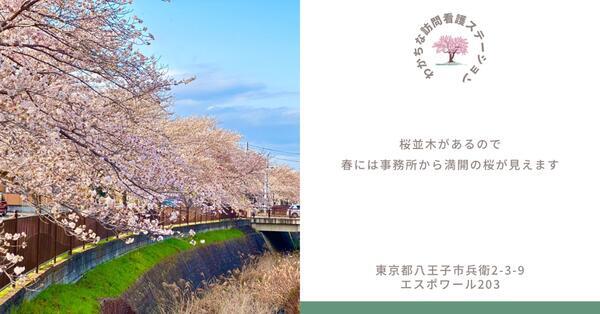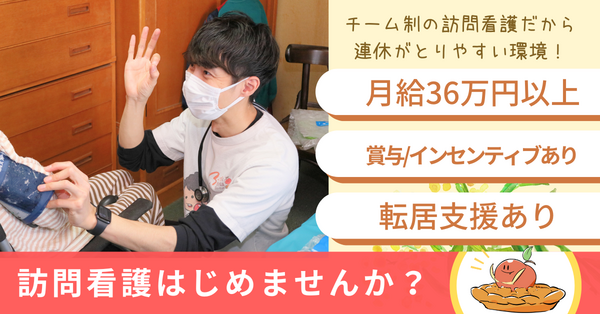未経験からでも安心!スタッフ想いの訪問看護ステーションで働くという選択|合同会社BLESSアップルパイ訪問看護ステーション
- 更新日

医療職としてだけでなく、一人の人間としてその人の人生に寄り添いたいー。そんな想いを胸に訪問看護の現場に立っているのが、東京都板橋区にあるアップルパイ訪問看護ステーションのスタッフたちです。利用者の病気や症状だけを見るのではなく、それぞれの生き方や価値観にも目を向け、暮らしそのものを支える。それが彼らの提供する訪問看護のあり方です。
運営母体である合同会社BLESSは、看護やリハビリといった医療的支援にとどまらず、精神疾患や発達障害をもつ若年層への支援、地域包括ケアの推進、地域イベントや勉強会の企画・実施など、多方面から地域と関わるステーションづくりを進める会社。スタッフの多くは20〜30代と若く、職種を越えてフラットに話し合え、助け合う文化が特徴です。仲間とともに切磋琢磨しながら、自分自身の成長も実感できる。そんな職場を目指し、日々のケアに向き合っています。
今回は、そんなステーションの管理者である小番(こつがい)さんに、アップルパイ訪問看護ステーションの職場としての魅力や働きやすさ、スタッフ育成の考え方、そして地域との関わり方について、たっぷりとお話を伺いました。
目次
1.自然体でいられる、あたたかい雰囲気

―アップルパイ訪問看護ステーションのスタッフ構成について教えてください。
当ステーションは看護師、理学療法士、作業療法士、事務スタッフなど、多職種で構成された20名ほどのチームで運営しています。平均年齢は30歳前後で、20代〜30代前半の若手スタッフが中心です。スタッフの年齢が近いこともあって、日頃から相談や情報共有がしやすく、非常に風通しの良い関係性です。
また、職種の垣根も感じにくく、例えば看護師がリハビリ職に相談することもあれば、逆にリハビリ職が看護の視点を求めることもあります。そうしたやりとりが日常的に行われているからこそ、チーム全体で一人の利用者さんを支える一体感を感じられるのだと思います。
―職場の雰囲気を一言で表すとしたら、どんな印象ですか?
そうですね。一言で言うなら「自然体でいられる空気感」でしょうか。もちろん訪問看護の現場では緊張感が必要な場面もありますが、ステーションに戻ってきたときには、みんなリラックスして過ごしています。年代が近いこともあり、スタッフ同士のちょっとした声かけや雑談も多くとても楽しい職場です。そんな雰囲気が日常的にあるからこそ、チーム全体で一人の利用者さんを支える一体感が生まれるのではないでしょうか。
―ライフステージに応じた働き方への配慮はありますか?
現在、産休・育休を取得しているスタッフも在籍しているなど、ライフステージに合った働き方にも柔軟に対応しています。また、子育て中のスタッフや、家庭の事情を抱えているスタッフも安心して働けるよう、シフトの調整や業務分担にも配慮しています。
まだまだ発展途上の部分もありますが、安心して長く働ける環境を目指しています。
2.訪問看護は「その人の人生を考える仕事」

―利用者の方にはどのような方がいらっしゃいますか?
基本的には高齢の方が多いですが、精神疾患を抱えている若年層や発達障害のあるお子さんなど、年齢や疾患の種類を問わず幅広い方々への訪問を行っています。そうした多様なニーズに対応できるのがこの事業所の強みです。
実際に20〜30代の方でうつ病や統合失調症、発達特性のあるお子さんの支援依頼があるなど、いわゆる“医療的ケア”に限らない支援も増えています。ご本人だけでなく、ご家族や周囲の支援者と一緒に「どうすればその人らしく暮らしていけるか」を考えるケースが多く、生活全体に目を向けた支援を意識しています。
―医療というより、その方の「暮らし」を支えている感覚が強いのですね。
そうですね。病院のように「治療」を目的とした支援とは異なり、訪問看護はその方がどのように毎日を過ごしたいのか、その生活の一部に関わる仕事です。たとえば、発達障害のあるお子さんの場合は、医療処置は一切ないケースも多いですし、精神疾患を抱えた方も、「この一週間どんなふうに過ごせていたか」を一緒に振り返るような関わりが中心になります。
何か具体的な症状を見るというよりは、「今日は顔色が少し暗いかな」「以前より笑顔が少なくなったかも」といった生活上の変化を細やかに感じ取り、そこから必要な支援につなげていくということが大切だと考えています。
ときにとても繊細な関わりにはなりますが、そのぶん少しずつでも利用者さんの表情が柔らかくなっていったり、生活が安定していく様子を見られたりすると、こちらとしてもあたたかな気持ちになりますね。
―訪問看護に必要な視点や姿勢にはどんなものがありますか?
一つは、「正解はひとつではないこと」に向き合える柔軟さだと思います。同じ疾患名であっても、利用者さんの生活環境や性格、ご家族の価値観、過ごしてきた人生の背景によって、必要な支援のかたちはまったく異なります。病院のように一定の流れの中で動ける環境とは違い、訪問看護ではその方の生活の中に自分が入っていくことになります。
私たちは医療職として一定の知識やスキルを持っていますが、それをマニュアル通りに提供するのではなく「この方にとって今、本当に必要な支援は何なのか?」を、日々の小さなやり取りや変化の中から丁寧に読み取っていく力が求められます。ときにはご本人から言葉にされないニーズを察知する必要もあり、まさに“感じる力”のようなものも身につける必要があるのです。
もうひとつ大切なのは、「その人自身を知ろうとする姿勢」です。疾患や障害の有無に関係なく、一人の人間としてその方を尊重し、向き合う姿勢は不可欠なものです。訪問先での何気ない会話の中に、その方らしさがにじみ出ていることもありますし、「どうしてこの暮らし方をしているのか」「どんな思いで今ここにいるのか」まで想像することで、本当に必要なサポートが見えてくることもあります。
ただ決められたケアを行うのではなく、生活や人生に寄り添うつもりで関わっていくこと。それが訪問看護の本質であり、最も大切にしたい姿勢だと思うのです。
3.経験が浅くても安心のサポートとやりがい

―訪問看護未経験でも活躍できますか?
実は現在働いているスタッフの9割は、訪問看護未経験からのスタートなんです。同行訪問では先輩スタッフが実際のケアや記録の仕方、他職種との連携方法までじっくりとお教えしますので、大きな心配はいりません。
また、入社後3ヶ月・6ヶ月・1年といった節目に面談の機会を設けており、現状の課題や目標をはじめ、悩みや想いなどにもしっかりと向き合っています。誰かと比較することなく、一人ひとりのペースに合わせて段階的に成長していける体制を整えているので、きっと安心して働いていただけると思います。
―スタッフ育成やスキルアップの支援体制について教えてください。
はい。研修参加や学会出席、専門書の購入など、学びに対する支援は積極的に行っています。外部研修にかかる費用の補助はもちろん、社内でも動画教材を活用した学習機会をつくっていますので、時間や場所に縛られずに知識が深められる環境です。
また、特定の領域に興味があればその分野での専門性も高められるよう、外部の勉強会や他のステーションとの交流も支援しています。実際に、現在大学院に通いながら働いているスタッフも在籍しており、そうした柔軟な働き方にも理解ある職場だと自負しています。
―ICTや業務効率のための工夫はありますか?
スタッフ全員にiPadとスマートフォンを支給しており、訪問記録や情報共有にはチャットツールを活用しています。こうしたツールは紙の記録よりも遥かに効率がいいですね。また、ちょっとした疑問や心配事もその日のうちに共有・解決できるよう、訪問前後の打ち合わせや朝礼・終礼などは大切にしています。
―地域連携やイベント活動についても伺いたいです。
私たちは「地域の中で生きる」という当たり前の暮らしを支える存在でありたいと考えています。そのため、大切にしているのは地域包括支援センターやケアマネジャー、クリニックとの連携を密にすることと、顔の見える関係性を維持することです。
希望したスタッフを中心に近隣病院の勉強会や事業者さんとの懇親会などには積極的に参加しています。連携先の訪問診療の先生や、ケアマネージャーさんと食事などをする機会も時折あり、地域を支えるチームとして何かあった時に相談しやすい関係づくりを大切にしています。社内の勉強会なども「こんなことをやってみたい」という声が上がれ ば、チーム全体で実現に向けて力を合わせています。
―小番さんが管理者として、大切にしていることは何ですか?
管理者という立場ではありますが、現場のスタッフと同じ目線でともに悩み、ともに考える存在でありたいと思っています。現場では正解のないケースも多く、誰かが一人で抱え込んでしまうとそれが負担になってしまうこともあるため、心がけていることは「スタッフが困ったときに、頼れる存在」であることです。
自分が管理する側だからといって上から指示を出すのではなく、まずは本人が「どう感じているのか」「何に迷っているのか」を丁寧に聞くことを大切にしています。そのうえで、一人ひとりの「こうしたい」「こうなりたい」という想いには真剣に向き合い、それを実現するためにはどんなサポートが必要か、そんなことを一緒に考えたいと思っています。
制度やルールはあくまでもベースであって、画一的に運用することが目的ではありません。誰かにとって必要なルールが、別の人にとっては負担になってしまうこともあります。だからこそ、その人の状況や価値観に応じて柔軟に対応することが、長く安心して働ける環境づくりには不可欠だと感じています。
また、こうした姿勢は私とスタッフの間だけではなく、スタッフ同士の信頼関係にもつながっていくと信じています。安心して「助けて」と言える職場であること、自分の意見が尊重されると実感できること。それが、スタッフ一人ひとりのモチベーションや定着に、大きく関わってくるのではないでしょうか。
―最後に、求職者の方へメッセージをお願いします。
訪問看護は、その人の暮らしに深く関わる仕事です。だからこそ、正解がないからこその面白さや、試行錯誤する中で見えてくる喜びがあります。
経験の有無に関わらず、相手に真摯に向き合う姿勢があれば、きっと活躍できる場所だと思います。「誰かの力になりたい」「地域とつながる仕事がしたい」そんな想いを持っている方と、ぜひ一緒に働けたら嬉しいです。まずは見学だけでも大歓迎ですので、気軽にステーションの雰囲気を見に来ていただけたらと思います。