【徹底解説!】認可・認可外保育園などの種類と働き方の違いについて
- 更新日
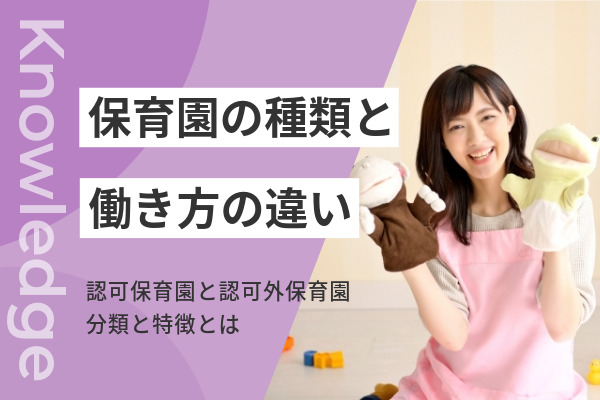
保育園には、認可保育園と認可外保育園があり、それぞれがいくつもの種類に分かれていて特徴に違いがあります。自治体によって名称や制度が違うこともあり、保育士でさえよく分からないという方が多いのではないでしょうか。
この記事では、保育園の種類とその特徴、それぞれの働き方などについて詳しく解説します。保育士の2025年問題や、働く保育園を選ぶ時のポイントについても紹介していますので、保育園への就職、転職をお考えの方はぜひ最後までご一読ください。
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!
目次
そもそも保育園とは?
そもそも保育園とはどのような施設なのでしょうか。まずは保育園の定義や役割、対象となる児童について確認していきましょう。
保育園の定義
保育園は、児童福祉法第39条により、次のように定義されています。
「保育所(保育園)は、保護者が労働、疾病、その他の事情により家庭で保育できない乳幼児を保育することを目的とする施設である。」
保育園とは、保護者が仕事や病気、介護などで子どもの面倒を見られない場合に、子どもを預かり保育する施設のことです。対象年齢は、0歳から小学校就学前の乳幼児で、入園条件として保育の必要性があることが求められます。
幼稚園は文部科学省管轄の教育施設で、教育を中心に行います。一方、保育園は厚生労働省管轄の福祉施設という位置付けで、保育を中心に行っています。
保育園が持つ役割
保育園は単に子どもを預かるだけでなく、子どもの成長や家庭・社会の支援を行う役割を担っています。保育園にとって一番大切なことは、子どもが安全で安心して過ごせる環境を提供することです。基本的な生活習慣の形成や社会性の発達、遊びや体験を通じて好奇心に刺激を与えることなどにより、子どもの健やかな成長を支えます。
共働き家庭やひとり親家庭など、保護者が働きながら子育てできるよう支援することも大きな役割のひとつです。保育園は、地域の子育て支援拠点としても機能しており、保護者だけではなく地域全体の教育環境をサポートしています。また、年齢に応じた教育的な活動を行うことで、言葉の発達や想像力、表現力を延ばす役割も担っています。
保育園の対象児童
認可保育園の対象児童は、親の就労や病気、妊娠、出産などにより家庭で保育することができない乳幼児です。一方、認可外保育園では、基本的に理由を問わず入園が認められています。
対象児童の年齢の範囲は、0歳(生後57日以上の乳児)から小学校就学前の5歳児までですが、保育園や自治体によって受け入れ可能な年齢は異なります。保育園の種類による対象児童の年齢範囲については後の章で詳しく解説します。
2種類の保育園の特徴と働き方
保育園は、厚生労働省が定めた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たしていることが必要です。そのうえで、都道府県知事や市区町村長の認可を受けている「認可保育園」と、認可を受けていない「認可外保育園」に分かれています。
「認可保育園」について
認可保育園の特徴と働き方について詳しくみていきましょう。
認可保育園は、面積や保育士の配置など、国が決めた基準をすべて満たしている施設です。自治体などが運営している公立保育園と、民間が運営している私立保育園があります。認可保育園の特徴について一覧表にまとめました。
| 目的 | 保護者の就労などにより、保育を必要とする児童を保育すること |
|---|---|
| 施設基準 | 自動福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令) |
| 面積基準 | 乳児室の面積:1.65㎡/人 ほふく室の面積:3.3㎡/人 |
| 保育従事者 | すべて保育士 ※0~2歳児を4名以上受け入れる場合、保健師・看護師・准看護師のいずれかひとりに限り保育士としてカウント可 |
| 申込・入園方法 | 保育所がある自治体に申し込み、自治体が選考する |
| 保育料 | 保護者の収入により決定(3~5歳児は無償) ※地域や保護者の収入により0歳児から無償の場合もあります |
認可保育園を利用するには、「家庭で日中の保育が困難であること」など、条件を満たしている必要があります。また、自治体によって入園できる優先順位などが定められています。
認可保育園で働く際には、公立であっても私立であっても、保育士資格が必須です。公立保育園で勤務する保育士は公務員になるため、常勤保育士として働くためには公務員試験に合格しなければなりません。一方、私立保育園に勤務する保育士は、保育士資格を保有し、保育園の採用試験に合格することで就業できます。
認可保育園の開園時間は、一般的に7時から19時で、延長保育がある場合には22時頃までです。そのため、保育士の勤務時間は早番(7時から16時)、中番(8時半から17時半)、遅番(10時から19時)、延長保育担当(11時から20時)といったようにシフト制のことが多くなっています。基本的に平日週5日勤務ですが、自治体や保育園によっては土曜出勤がある場合もあります。
認可外保育園に比べて、給与は若干少ないことが多いものの、福利厚生は比較的充実している場合がほとんどです。公立の認可保育園の保育士は公務員扱いとなるため、自治体にもよりますが、給与・福利厚生面が手厚い傾向にあります。
「認可外保育園」について
認可外保育園の特徴と働き方について詳しくみていきましょう。
認可外保育園は、都道府県知事や政令指定都市の市長の認可を受けていない保育園のことです。認可保育園ほど細かな基準はありませんが、認可外保育園を実際に運営するためには「認可外保育施設指導監督基準」を満たさなければなりません。認可外保育園の特徴について、一覧表にまとめました。
| 目的 | 保育を希望する保護者の委託を受けて、児童を保育すること |
|---|---|
| 施設基準 | 認可外保育施設指導監督基準(厚生労働省通知) |
| 面積基準 | 乳児室の面積:1.65㎡/人 |
| 保育従事者 | 保育従事者の3分の1以上は保育士または看護師 |
| 申込・入園方法 | 保育園に直接申し込みし、保育園が選考する |
| 保育料 | 保育園ごとに自由に設定 |
認可外保育園には、国や自治体から運営費の支給や補助金などがありません。保育料は保育園側が自由に設定できるので、施設ごとに料金が大きく違います。また、保育についての審査基準などがないため、独自の保育方針を立てることができ、保育園ごとに保育内容が異なるのが特徴のひとつです。
認可外保育園は認可保育園と違い、保育の必要性がない子どもでも利用可能です。保護者の就労状況や勤務時間を問わず、最長13時間の長時間保育を行っています。
認可外保育園で働く保育士はシフト制であることが多く、パートやアルバイトとして短時間での勤務も可能です。また、資格なしでも働くことができます。保育園によっては早朝や深夜、24時間保育を行っていることもあり、勤務時間は柔軟な場合が多いです。土日祝日も開園している保育園では、土日勤務が発生することがあります。
認可外保育園は、給与面では認可保育園よりやや高い傾向にありますが、実際には園によってさまざまです。社会保険やボーナス、退職金といった福利厚生面では、認可保育園に比べて劣ることが多いようです。
職場環境としては少人数保育が多く、独自の保育方針を持ち、特色ある保育や教育をしています。そのため、保育士にとっても自分に合った保育園を選べる面白さがあることが特徴のひとつです。保育園によってルールや方針に違いがあるので、働きやすさといった面では園ごとに差があります。働く環境が園の方針によって大きく左右されるので、入職前のリサーチが非常に重要です。
「認可保育園」に分類される保育園を紹介!
認可保育園に分類される保育園は、「認可保育所」「認定こども園」「地域型保育事業」に大別されています。地域型保育事業はさらに分類されているので、それぞれについて詳しくみていきましょう。
1)認可保育所
認可保育所は、国や自治体の基準を満たし、認可を受けた保育施設です。施設の広さや職員数、設備など、国が定めた設置基準を満たしている必要があります。保護者の就労や病気などにより、自宅で保育することが難しい0歳から5歳までの未就学児が対象です。
2)認定こども園
認定こども園は、幼稚園と保育園の両方の特徴を持ち、自治体からの認可を受けて運営している施設です。教育と保育の両方を提供しており、幼児教育が充実しているのも特徴です。親の就労状況に関わらず利用することができ、対象児童は0歳から5歳までの就学前の子どもとなっています。認定こども園は、長時間の預かりが可能なこと、幼児教育が受けられるといった幼稚園と保育園の良いところを併せ持った施設です。
3)地域型保育事業
地域型保育事業は、2015年の「子ども・子育て支援制度」により制度化された事業で、0歳から2歳児を対象とした小規模な保育サービスです。この制度は、特に都市部などで待機児童問題を解消するために導入されました。地域型保育事業はA型からD型まで4つの種類に分かれているので、それぞれについて解説します。
小規模保育事業は、定員が6人から19人の小規模な保育施設です。自治体の認可を受けており、保育料は保護者の所得に応じて決まります。定員が少ないため、家庭的な雰囲気で保育が行われるのが特徴です。対象年齢は従来0歳から2歳まででしたが、2023年に0歳から5歳までに拡大されました。施設の規模が小さいため、設備や園庭の面積が限られている場合があり、園によっては散歩や外部施設を活用するといった工夫をしています。
1人から5人程度の子どもを、保育士や保育ママと呼ばれる、自宅で保育を行う方に預けるタイプのサービスです。家庭的保育事業を運営するには、自治体の認可が必要です。家庭的保育事業は個別の対応がしやすいので、大人数の環境が苦手な子どもや、特別な配慮が必要な子どもにとって過ごしやすい環境を提供できるサービスになっています。対象年齢は0歳から2歳までです。
事業所内保育事業は、企業が従業員の子どもを預ける目的で事業所内に設置している保育施設です。事業所内保育事業は、自治体の認可を受けている施設と受けていない施設があります。こちらに分類されるのは、自治体の認可を受けた施設です。企業によっては、地域の子どもも受け入れしている場合もあり、対象年齢は0歳から2歳までです。
傷害や病気、保護者の夜間就労など、特別な事情がある子供に対して、保育士が家庭を訪問して保育を行うサービスです。こちらも自治体の認可が必要です。必要な研修を受け、市区町村に認められた家庭的保育者が保育を行います。対象年齢は0歳から2歳までです。
「認可外保育園」に分類される保育園を紹介!
認可外保育園は、「認証保育所」「居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)」「その他の認可外保育施設」に大別されています。その他の認可外保育施設はさらに分類されているので、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1)認証保育所
認証保育所は、東京都や横浜市、名古屋市など、特定の自治体で設置されている認可外保育施設の一種です。認可保育園と同様、一定の水準を守るために自治体の基準を満たしていることが必要です。定員は比較的小規模で、通常20人から30人程度に設定されています。認証保育所では認可保育園と同様、保育士による保育が行われ、施設の安全性や衛生面も管理されています。
2)居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)
居宅訪問型保育事業は、保育士が利用者の自宅に訪問し、家庭で子供を保育するサービスです。特に家庭での保育が難しい事情のある場合や、特別な支援が必要な子どもに対して利用されています。子ども一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかな支援ができる点、保護者と保育士が協力して子供の育成をサポートできる点がメリットです。働く保育士にとっては、移動を伴い、複数の家庭を訪問することになるため、業務負担は大きい場合があります。
3)その他認可外保育施設
認可外保育施設には、認証保育所、居宅訪問型保育事業以外にもさまざまな種類があります。主な施設についてみていきましょう。
院内保育所は、病院や医療機関内に設置された保育施設です。主に病院で働く医療従事者の子どもを対象にしています。勤務形態が不規則になりやすい医療従事者向けに、24時間保育や夜間保育に対応していることが多いのが特徴です。病院が直接運営しているケースと、外部の保育事業者に委託しているケースがあります。施設の規模が小さいため、受け入れ枠に限りがあります。また、保育士として働く場合には、夜間対応が必要な場合があることを覚えておいてください。
企業主導型保育所は、企業が従業員のために設置している保育施設です。2016年度から開始された制度で、内閣府が所管し、国からの補助金で運営されます。企業が直接運営しているケースと、外部の保育事業者に委託して運営しているケースがあります。対象年齢の制限がないのが特徴です。
事業所内保育事業は、2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」において、「地域型保育事業」の一つとして位置づけられた認可保育事業です。一定の基準を満たせば、自治体からの給付を受けることができます。対象年齢は原則0歳児〜2歳児となっています。
ベビーホテルは、子どもを一時的に預かる施設です。保護者に急な用事ができた場合などに、子どもを一時的に預けるために利用されています。ベビーホテルにはベビーベッドやお昼寝用のスペースが用意されており、宿泊が可能です。保育士や看護師が常駐し、安全対策が施された清潔で快適な環境が整っています。より高度なサービスや設備が整った高級施設も存在しています。
幼稚園類似施設等とは、児童数や設備面において、国が定めた基準を満たしていないものの、幼稚園と同様の教育を提供している施設のことです。保育時間やカリキュラムは施設によってさまざまです。対象年齢は3歳から5歳の幼児で、幼児教育を重視しています。認可外施設ですが、自治体の補助を受け、企業やNPOが独自の教育方針で運営しています。保育時間は幼稚園と同じく、午前中が中心のところがほとんどです。幼稚園類似施設は、独自の教育・保育方針や特色が強く、特定のニーズを持つ保護者に支持されています。
保育園が抱える問題
保育園が抱える問題は、保育者として就職するにあたってチェックしておく必要があります。現在保育園が抱えている問題にはどのようなものがあるのか、詳しく解説します。
施設数と利用者数の推移
近年、保育園などの施設数は増加しており、利用者もここ10年ほどで1.4倍程度に増えています。特に幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園の数は増加の一途です。働く母親が増えたことで、幼稚園よりも預かり時間が長い保育園やこども園を選ぶ保護者が増えたことが主な理由と推察されています。
待機児童数の推移
待機児童数は、少子化の影響もあり、ここ10年で10分の1程度まで減少しています。少子化による子どもの減少と、少子化対策による保育園などの増加により、保育園の受け入れ態勢は整いつつあります。しかし、地域によっては依然として待機児童が存在している状況です。特に1歳から2歳の乳幼児の利用率が年々増加しており、引き続きの対応が求められています。
保育士の2025年問題
2025年問題とは、日本の総人口のおよそ2割が75歳以上の後期高齢者となり、社会保障制度や医療、介護など、さまざまな分野に影響を及ぼすことが懸念されている社会問題です。2025年問題は保育士にとっても無視できない課題です。2021年に厚生労働省が発表した「保育を取り巻く状況について」によれば、保育園を利用する児童数は2025年にピークとなり、以降は緩やかに減少していくことが見込まれています。
待機児童問題では、保育園と保育士の数が足りない状態でしたが、今後は少子化による子どもの減少により、徐々に保育園余り、保育士余りが起こると予測されています。実際に予想されているのは、保育園の閉園や統合です。また、保育園余りが起こることで、園ごとに入園を希望する児童に偏りが起こる可能性があります。
保育士にとっても少なからず影響があり、将来的には給与や賞与が減額される可能性があります。十分な入園者を確保するため、保育者も経験値やスキルを上げて、保育の質を高めることに力を入れなければならない時代がすぐそこまで迫っています。就職や転職する保育園を選ぶ際には、入園者をこれからもしっかりと確保し続けることができる、信頼性と魅力を兼ね備えた園を見極めることが大切です。
働く保育園を選ぶときのポイントとは?
ここまで保育園の種類や問題点についてもみてきましたが、最後に働く保育園を選ぶ時のポイントについて確認しておきましょう。
【ポイント1つ目】情報収集をしよう!
保育園選びに最も大切なのは情報収集です。求人サイトのチェックはもちろん、保育士の転職セミナーや転職エージェントへの登録もおすすめです。保育園を利用している保護者が投稿している口コミなどもみてみると、実際の園の雰囲気を知ることができます。
【ポイント2つ目】労働条件や給料面をよくみてみよう
働く保育園を選ぶ際には、労働条件や給与面についてもよく確認しましょう。勤務形態が固定勤務なのかシフト勤務なのか、土日は休むことができるのか、残業の有無などについて、求人票に載っていない場合には面接で確認することをおすすめします。長く安定的に働くためには、労働条件と給与面が自分にとって納得いくものであることが非常に重要です。
【ポイント3つ目】福利厚生にも目を向けてみよう!
就職先を決める際に意外と注目されていない福利厚生ですが、長く働くうえでは大きな差が出る場合があります。一見、給与は低い場合でも、福利厚生が手厚いということもあります。長期にわたって働く予定であれば、給与と同様、福利厚生についてもチェックしておきましょう。
【ポイント4つ目】可能ならば職場見学に行こう!
就職したいと思える保育園が見つかったら、面接の前に職場見学できるか確認してみましょう。施設の状況や職員の雰囲気、保育士と子どもの関係性などを自分の目で見ることにより、求人票ではわからないさまざまなことがみえてきます。実際に見学に行くことで、通勤のしやすさについても確認できるので、複数の施設を見学して比較してみるのがおすすめです。
まとめ
保育園には、認可・認可外の違いだけでなく、さまざまな種類があり、それぞれの施設に特徴や働き方の違いがあります。認可保育園は、基準が厳格で安定した環境が整っています。一方、認可外保育園は柔軟な運営が可能で、多様な保育ニーズに応えることが可能です。
保育士として働く場合には、それぞれの園の特徴を理解し、自分に合った環境の施設を選ぶことが大切です。保育業界の現状も踏まえたうえでより良い選択ができるよう、本記事が参考になれば幸いです。
事業所からスカウトがくる!
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!










