児童発達支援管理責任者(児発管)とは? 仕事内容、給料、なり方を徹底解説
- 更新日
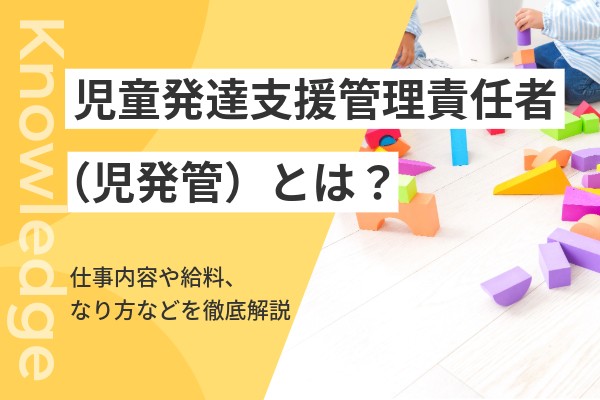
子どもの成長を支援する仕事に興味がある方、または現在福祉の現場で働いていてキャリアアップを考えている方にとって、「児童発達支援管理責任者(児発管)」は、非常に注目度の高い職種でしょう。
近年、発達に特性のある子どもたちへの支援の重要性が高まる中で、児発管は彼らの成長を支える上で欠かせない存在となっています。しかし、「具体的にどんな仕事をするの?」「どうすればなれるの?」「給料はどれくらい?」といった疑問を抱えている方も少なくないはずです。
この記事では、児発管の役割や具体的な仕事内容から、資格取得への道のり、気になる給料・年収、そして就業先や仕事のやりがいまで、児発管に関するあらゆる疑問を徹底的に解説します。この記事を読めば、児発管という仕事の全体像を深く理解し、あなたのキャリアを考える上で役立つ情報がきっと見つかるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!
目次
児童発達支援管理責任者(児発管)とは
児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がいを持つ子どもたちをサポートする専門職です。児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援事業所において、サービスの質を保証し、支援全体を統括するリーダーとしての役割を担います。
その存在は、2012年の児童福祉法と障害者自立支援法の改正により、障がい児支援の強化を目的として新設されたもので、児童福祉法に基づく指定事業所には、原則として1名以上の配置が義務付けられています。
児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事内容
児童発達支援管理責任者(児発管)の主な仕事内容は以下の通りです。
個別支援計画の作成と管理
児発管の最も中心的で専門的な業務が、この個別支援計画の作成と管理です。障がいを持つ子ども一人ひとりの発達状況、特性、得意なことや苦手なこと、家庭環境、そして保護者の意向を詳細に把握することから始めます。
アセスメント(現状分析)を通じて、その子にとって最適な支援目標を設定し、具体的な支援内容、支援の提供方法、評価の視点などを盛り込んだ「個別支援計画」を作成します。この計画は一度作って終わりではなく、子どもの成長や環境の変化に応じて、少なくとも6ヶ月に1回以上は見直しを行い、必要に応じて修正を加え、常に最適な支援が提供されるよう管理していきます。
相談業務と保護者支援
子どもたちだけでなく、その保護者への支援も児発管の重要な役割です。子育てに関する悩み、障がいの特性理解、将来への不安など、保護者からの様々な相談に応じます。
専門的な知識と経験に基づき、適切なアドバイスや情報提供を行うことで、保護者が安心して子どもを預け、前向きに子育てに取り組めるようサポートします。信頼関係を築き、保護者にとって頼れる存在となることが求められます。
人材育成と指導
児発管は、事業所のサービス提供の責任者として、他の支援員や指導員を束ねるリーダーでもあります。個別支援計画に基づき、他のスタッフが適切な支援を行えるよう、具体的な指示や助言、技術指導を行います。支援の質の向上を図るための研修の企画・実施や、スタッフのメンタルヘルスケア、より良い職場環境づくりなども児発管の仕事に含まれます。
関係機関との連携・調整
子どもを取り巻く様々な関係機関との連携も、児発管の重要な役割です。保育所、幼稚園、学校、医療機関、地域の相談支援事業所などと密に連携を取り、情報共有や支援内容の調整を行います。これにより、事業所内だけでなく、子どもが生活する全ての場において、一貫性のある適切な支援が提供されるよう橋渡し役を担います。
緊急時対応と安全管理
子どもたちが安全にサービスを利用できるよう、緊急時の対応や安全管理体制の整備も児発管の重要な業務です。地震や火災などの災害時、子どもの体調急変時、事故発生時など、あらゆる緊急事態を想定し、マニュアルの作成や避難訓練の実施、迅速かつ適切な対応を行います。
日頃から危険箇所の確認や安全対策を徹底し、子どもたちが安心して過ごせる環境を維持する責任があります。
事務作業・その他
個別支援計画書やモニタリング記録の作成、利用者の状況報告、国保連への請求業務など、多岐にわたる事務作業も児発管の業務です。事業所によっては、送迎業務や簡単な清掃、イベントの企画・運営などに携わることもあります。子どもの支援に直接関わる業務だけでなく、事業所運営を円滑に進めるための裏方としての役割も担います。
児発管の1日の流れ
児発管の1日は、事業所の規模や子どもの状況によって様々ですが、一般的な流れとしては以下のようになります。
08:30 出勤・朝礼、情報共有
09:00 個別支援計画の作成・見直し
10:30 関係機関との連携・調整
11:30 教材・プログラム準備、スタッフへの指示
12:00 昼休憩
13:00 利用児童の迎え入れ・健康チェック(児童発達支援の場合)
13:30 集団活動・個別支援の見守り・指導
15:00 おやつ・休憩(放課後等デイサービスの場合、この時間から利用開始が多い)
15:30 個別支援・集団活動の実施(放課後等デイサービスの場合)
17:00 保護者対応・申し送り
17:30 利用児童の見送り
18:00 記録作成・終礼
18:30 清掃・戸締り、退勤
児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?
障がいを持つ子どもたちの成長を支える専門職、児童発達支援管理責任者(児発管)になるには、定められた実務経験と研修の修了が必要です。ここでは、その具体的なステップと、目指す上での注意点について解説します。
児発管になるまでのステップ
児発管になるには、以下の段階を踏む必要があります。
まず、障がいのある方や子どもへの支援に関する実務経験が必要です。これは大きく分けて「相談支援業務」と「直接支援業務」の2種類があり、保有する資格によって必要な期間が異なります。
- 相談支援業務:相談支援事業所などで相談援助を行う業務。原則として5年以上の経験が求められ、そのうち3年以上は障がいのある方または子どもを対象とした業務である必要があります。
- 直接支援業務:施設などで利用者の身体介護や生活支援を行う業務。原則として8年以上の経験が求められ、そのうち3年以上は障がいのある方または子どもを対象とした業務である必要があります。
- 特定の国家資格(保育士、社会福祉士、看護師など)保有者:これらの資格を持つ場合、相談支援業務または直接支援業務の経験が5年以上(うち3年以上は障がいのある方または子ども対象の業務)に短縮されるケースがあります。
注意点として、実務経験の範囲や期間の数え方は、都道府県によって異なる場合があります。 必ずご自身が児発管として働こうと考えている地域の最新の要件を確認しましょう。
実務経験の要件を満たす、または満たす見込みが立った段階で、基礎研修を受講します。この研修は、児発管として必要な個別支援計画作成の基礎や障がい児支援に関する知識、倫理などを学ぶ座学と演習で構成されます。実務経験要件を満たす予定の2年前から受講が可能です。
基礎研修を修了した後、すぐに児発管として配置されるわけではありません。基礎研修修了後、児発管の業務として、個別支援計画の作成や評価に関する実践的な経験を2年以上積む必要があります。これがOJT(On the Job Training:現場での実践)期間です。この期間中に、先輩児発管の指導のもと、支援計画の補助や会議への参加を通じて、児発管としての実務能力を培います。
※2023年の法改正により、条件によっては6ヶ月以上のOJTで実践研修の受講が可能となる場合があります。
OJT期間(2年間)を修了した後、実践研修を受講します。この研修では、基礎研修で学んだ内容をさらに深掘りし、個別支援計画の実践的な作成方法、人材育成、地域との連携など、より高度な専門知識とスキルを習得します。この実践研修を修了することで、正式に児童発達支援管理責任者として配置される資格が得られます。
児発管として配置された後も、資格を維持するためには継続的な学習が必要です。実践研修または前回の更新研修修了後、5年ごとに更新研修の受講が義務付けられています。これを怠ると、児発管としての資格を喪失する可能性がありますので注意しましょう。
児発管になるために注意するポイント!
児発管を目指す上で、特に気をつけたいポイントは以下の通りです。
これが最も重要です。ご自身のこれまでの職歴が児発管の求める実務経験に該当するか、期間は足りているか、具体的な業務内容は認められるかなど、必ず事業所がある都道府県の担当部署に確認しましょう。曖昧なまま進めると、後で資格が認められないという事態になりかねません。
児発管の研修制度は近年見直しが行われています。最新の情報を常に確認し、古い情報に惑わされないようにしましょう。各都道府県のウェブサイトや研修実施団体の情報をチェックすることが大切です。
基礎研修後の2年間のOJT期間は、単に時間を過ごすだけでなく、実際に児発管としての業務に深く関わることが求められます。所属する事業所が適切なOJTを提供できる体制にあるかどうかも確認ポイントです。
児発管は、単に資格を持つだけでなく、高いコミュニケーション能力、アセスメント力、リーダーシップ、問題解決能力、そして何よりも子どもたちへの深い愛情と責任感が求められます。これらの資質を向上させる意識を持つことが大切です。
実務経験、基礎研修、OJT、実践研修と段階を踏むため、児発管になるにはある程度の期間が必要です。自身のキャリアプランを見据え、逆算して計画的に準備を進めましょう。
児発管は責任が大きい一方で、子どもたちの成長を間近で見守り、その可能性を最大限に引き出すことができる、非常にやりがいのある仕事です。これらのポイントを押さえて、着実にステップアップを目指してください。
児童発達支援管理責任者(児発管)の給料
厚生労働省が令和4年10月に行った調査によると、児童発達支援管理責任者(児発管)の給与状況は、常勤職員で月額278,480円、非常勤職員で月額140,085円となっています。
この金額はあくまで全国平均であり、実際の給与は地域、施設の規模、運営形態、個人の経験年数やスキル、さらには保有資格といった様々な要因によって変動します。しかしながら、このデータは児発管の給与水準を把握する上で、一つの重要な目安となるでしょう。
参照:厚生労働省「令和 5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」
施設形態別給与データ
施設形態 |
常勤 |
非常勤 |
|---|---|---|
児童発達支援 |
204,926円 |
220,844円 |
医療型児童発達支援 |
410,377円 |
- |
放課後等デイサービス |
297,487円 |
154,286円 |
居宅訪問型児童発達支援 |
292,960円 |
86,000円 |
保育所等訪問支援 |
302,511円 |
113,102円 |
福祉型障害児入所施設 |
382,122円 |
- |
医療型障害児入所施設 |
330,175円 |
- |
参照:厚生労働省「令和 5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」
常勤の児発管として働く場合、最も月額給与が高い傾向にあるのは医療型児童発達支援施設で、410,377円となっています。これは、医療的ケアが必要な児童への支援を専門とすることから、より高度な専門性や知識が求められるためと考えられます。
次に高いのは福祉型障害児入所施設で382,122円、医療型障害児入所施設が330,175円と続きます。これらの入所施設は、24時間体制での支援や、より重度な障がいを持つ子どもたちへの対応が必要となるため、給与水準も高めに設定されていると推測できます。
その他の施設形態では、保育所等訪問支援が302,511円、放課後等デイサービスが297,487円、居宅訪問型児童発達支援が292,960円となっています。これらの施設は、比較的一般的なサービス形態であり、児童発達支援の分野で最も求人数が多い部類に入ります。一方、最も給与が低いのは児童発達支援施設で204,926円です。これは、事業所数が非常に多く、サービス内容も多岐にわたるため、平均値が低くなっている可能性があります。
非常勤の児発管として働く場合、最も高いのは児童発達支援施設で220,844円です。これは、同施設が提供するサービスの幅広さや、専門性の高い業務が非常勤にも任される可能性があるためと考えられます。
次に高いのは放課後等デイサービスで154,286円です。学校終了後の支援という特性上、非常勤の需要が高い施設です。保育所等訪問支援は113,102円、そして居宅訪問型児童発達支援は86,000円となっています。居宅訪問型は、利用者宅への訪問を伴うため、移動時間も考慮するとこの金額になるのかもしれません。
非常勤の給与は、施設の形態だけでなく、実際の勤務時間や日数に大きく左右されます。提示された金額はあくまで月額平均であり、週の勤務日数や時間によって実際の収入は変わってきます。また、経験年数や担当する業務内容によって時給や日給が変動することもあります。ご自身のライフスタイルと希望する給与のバランスを考慮し、最適な職場を探すことが重要です。
児童発達支援管理責任者(児発管)の就業先
児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がいを持つ子どもたちへの支援を提供する様々な事業所で活躍しています。その主な就業先は、児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業所や障がい児入所施設などです。ここでは、児発管が働く主な事業所について解説します。
児童発達支援事業所
児童発達支援事業所は、主に未就学の障がいを持つ子どもたち(0歳〜就学前)が通所し、療育を受ける施設です。日常生活動作の指導、集団生活への適応支援、遊びを通じた発達支援など、個々の発達段階に応じた支援を提供します。
児発管は、利用する子ども一人ひとりの個別支援計画を作成し、他の指導員と連携しながら、その子に最適な支援が行われるよう統括します。家庭との連携も密に行い、保護者への助言や相談支援も重要な役割です。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、就学中の障がいを持つ子どもたち(小学生〜高校生)が、放課後や夏休みなどの長期休暇中に利用する福祉サービスです。学校教育と連携しながら、自立支援や集団生活への適応、居場所作りなどを目的とした支援を行います。
例えば、宿題のサポート、運動プログラム、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、創作活動など、多様なプログラムが提供されます。児発管は、学校や家庭との連携を密にし、個別支援計画に基づいた質の高い支援を提供できるよう、全体の管理・運営を担います。
医療型児童発達支援センター
医療型児童発達支援センターは、医療的なケアや専門的なリハビリテーションが必要な障がいを持つ子どもたちが利用する施設です。通常の児童発達支援に加え、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職が常駐し、医療と福祉が一体となった支援を提供します。
重症心身障がい児などの医療ニーズの高い子どもたちが主な対象となります。児発管は、医療スタッフと連携しながら、医療的な視点も踏まえた個別支援計画を作成・管理し、包括的な支援を調整する役割を担います。
保育所等訪問支援事業所
保育所等訪問支援事業所は、障がいを持つ子どもが通う保育所、幼稚園、小学校などを児発管や児童指導員などが訪問し、集団生活への適応を支援するサービスを提供します。子どもの特性に応じた具体的な支援方法を園の職員に助言したり、集団生活の中で困難を抱える子どもへの個別的なサポートを行ったりします。
児発管は、訪問先での子どもの状況をアセスメントし、訪問計画を作成するとともに、園の職員や保護者、関係機関との連携を密に取りながら、子どもがスムーズに集団生活を送れるようサポートします。
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどにより、外出が困難な子どもたちの自宅に訪問して支援を行うサービスです。移動が困難な子どもや、医療的ケアが必要な子どもなどが対象となります。日常生活動作の練習、遊びを通じた発達支援、家族への相談援助など、自宅という環境の中で、その子に合わせたきめ細やかな支援を提供します。
児発管は、利用者の自宅を訪問し、個別支援計画に基づいた支援を行うとともに、保護者との密な連携を図り、家庭での生活の質の向上をサポートします。
児童発達支援管理責任者(児発管)のやりがい
児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がいを持つ子どもたちの成長をサポートする非常に専門的で責任のある仕事ですが、その分大きなやりがいを感じられる職種でもあります。
子どもの成長を実感できる
児発管の仕事の最大のやりがいは、何と言っても子どもたちの小さな、しかし確かな成長を間近で実感できることです。一人ひとりの個性や発達段階に合わせた個別支援計画を立て、それが実を結び、できなかったことができるようになる瞬間を目の当たりにする喜びは格別です。
例えば、これまで発語が難しかった子が初めて言葉を発した時、友達と協力して遊べるようになった時、着替えが一人でできるようになった時など、それぞれの「できた!」を共有できることは、児発管にとって何物にも代えがたい達成感となります。子どもたちの可能性を信じ、それを引き出す手助けができることは、この仕事の醍醐味と言えるでしょう。
保護者の笑顔に触れる
障がいを持つ子どもの子育ては、保護者にとって喜びであると同時に、多くの悩みや不安を伴うことも少なくありません。児発管は、そうした保護者の声に耳を傾け、専門的な知識と経験でサポートする「伴走者」でもあります。
適切な支援によって子どもの発達が促され、保護者の不安が軽減され、安心や喜びで満たされた保護者の笑顔に触れることは、児発管にとって大きな励みとなります。保護者との信頼関係を築き、「ありがとう」の言葉を受け取った時、この仕事の重要性と価値を改めて感じることができます。
社会貢献への実感
児発管の仕事は、障がいを持つ子どもたちが地域社会で自立し、豊かな生活を送れるよう支援するという、非常に公共性が高く、社会貢献性の大きな役割を担っています。適切な支援が提供されることで、子どもたちが自身の能力を最大限に発揮し、社会の一員として生き生きと活動できるようになります。
少子高齢化が進む現代において、すべての子どもたちが健やかに成長できる環境を整備することは、社会全体の発展に繋がります。児発管としてその一翼を担い、地域社会に貢献できているという実感は、日々の業務へのモチベーションを高めてくれます。
専門性を高められる
児発管は、個別支援計画の作成や他のスタッフへの指導、多機関との連携など、幅広い専門知識とスキルが求められる職種です。そのため、常に新しい情報を取り入れ、学び続ける必要があります。研修への参加や、他の専門職との連携を通じて、自身の専門性を継続的に高めていけることは、自己成長を求める人にとって大きな魅力です。
複雑なケースに向き合い、様々な視点から解決策を探る過程で、福祉や教育、医療の知識を深め、人間としても大きく成長できる機会が豊富にあります。専門職としてのキャリアを築き、自身のスキルが子どもの未来に直結するという手応えを感じられるでしょう。
まとめ
児童発達支援管理責任者(児発管)は、発達に特性のある子どもたちの成長を多角的にサポートし、その可能性を最大限に引き出すための重要な役割を担う専門職です。個別支援計画の作成から保護者支援、人材育成、関係機関との連携、そして事業所の安全管理まで、その仕事内容は多岐にわたります。
子どもたちの「できた!」という喜びや、保護者の「ありがとう」という感謝の言葉は、児発管として働く上で、何物にも代えがたい宝物となるでしょう。社会貢献性が高く、大きな達成感を得られるこの仕事は、あなたのキャリアに新たな可能性をもたらすはずです。
もしあなたが、子どもたちの未来を支える仕事に情熱を持ち、自身の専門性を高めたいと考えているなら、児童発達支援管理責任者という選択肢は、きっとあなたの期待に応えてくれるでしょう。ぜひこの記事を参考に、児発管への第一歩を踏み出してみてください。
事業所からスカウトがくる!
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!










