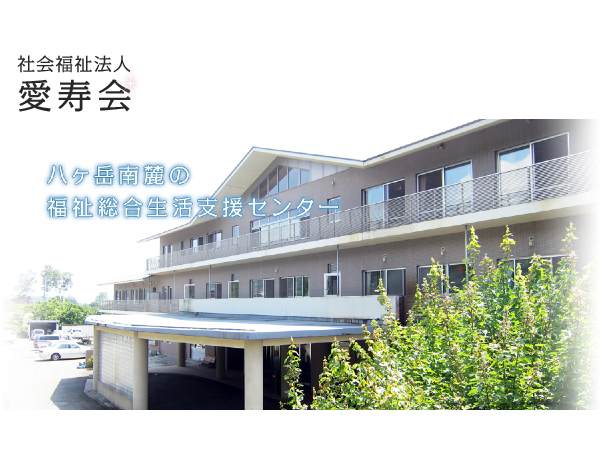放課後等デイサービス(放デイ)ってどんなところ?基礎知識から施設選びのコツまで
- 更新日

子どもの発達支援や療育について調べている時によく目にする放課後等デイサービス(放デイ)。この記事を読む方の中には「放デイの支援内容や利用方法が分からない」「放デイの仕事に興味があるけど、どんな資格が必要なの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、放デイの利用条件や支援内容などの基礎知識を徹底解説。放デイを利用したい方・放デイで働きたい方の両者にとって分かりやすい記事となっています。最後には放デイについてよくある質問をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!
目次
放課後等デイサービス(放デイ)とは?
放課後等デイサービスとは、発達障害など、支援が必要な小学生から高校生のお子さんが、学校の授業が終わった後や学校がお休みの日に利用できる福祉サービスです。分かりやすく言うと、「障害のあるお子さんのための学童保育」のようなイメージです。
放課後等デイサービスは、略称として「放デイ」がよく使われます。この記事でも、以降は放デイの表記とさせていただきます。
主な3つの目的
放デイの目的は、お子さんだけでなく保護者の支援を含みます。
- お子さんの自立支援と成長のサポート:個々のお子さんの特性や発達段階に合わせて、生活能力の向上に必要な訓練(例:着替え、手洗い、片付けなど)、学習支援、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などを通して、将来の自立や社会参加を促します。
- 居場所作りと社会性の育成:学校や家庭とは異なる場所で、他の子どもたちやスタッフとの関わりを通じて、集団生活のルールを学んだり、友達と過ごす中で社会性を育んだりする「居場所」を提供します。
- 保護者の支援:子育ての悩み相談に乗ったり、一時的に子どもを預かることで保護者の時間的・精神的な負担を軽減したりする役割も担っています。
SSTは「ソーシャルスキルトレーニング」の略で、英語で書くと "Social Skills Training" です。簡単に言うと、人が社会の中で生活していく上で必要となる「人との関わり方」や「上手な振る舞い方」を練習する場のことです。例えば以下を練習します。
- あいさつや返事の仕方
- 自分の気持ちの伝え方
- 人の話を聞く練習
- 友達との関わり方
- 困った時の対処法
SSTは、お子さんが社会の中で「生きやすくなる」ための、とても心強いサポートです。放デイでは、お子さんの特性に合わせて、専門のスタッフが丁寧に関わってくれます。
誰が利用できるの?(対象者)
対象年齢は、原則として6歳(小学校1年生)から18歳(高校3年生)までの就学児童です。対象条件は、以下の通りです。
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のあるお子さん
- 医師や自治体の保健センターなどによって、療育や支援の必要性が認められたお子さん
障害者手帳の有無は問われません。診断書や意見書などで支援の必要性が認められれば利用可能です。
平日だけでなく休日・長期休暇も対応
「放課後」という名前で勘違いされやすいですが、放デイは平日だけでなく、土曜日や日曜日、夏休みなどの長期休暇中も利用できます。学校の授業がない日も、お子さんの居場所となり、必要な支援を受けることができます。
ただし、事業所によって開所している曜日や時間は異なりますのでご注意ください。
放デイと児童発達支援の違い
放デイと児童発達支援はいずれも障害のある子どもを対象とした福祉サービスですが、対象年齢に違いがあります。
- 放デイ:6歳から18歳までの就学しているお子さん
- 児童発達支援:6歳までの未就学のお子さん
児童発達支援は、障害のあるお子さんの保育園や幼稚園のような役割と考えるとイメージしやすいかもしれません。
放デイと学童保育(放課後児童クラブ)の違い
放デイと学童保育は、どちらも学校の放課後や長期休暇中に子どもを預かる施設ですが、対象となる子どもや目的、提供される支援内容に違いがあります
学童保育は、原則として保護者が日中家庭にいない小学生(主に低学年)のお子さんが対象です。子どもの生活の場と遊びの場の提供が主な目的で、サービス内容は自由遊び、宿題の見守りが中心です。
対して、放デイは障害のある小学生から高校生までが対象で、自立支援と成長のサポートを目的に生活訓練を行います。
スカウトサービス登録はこちら放デイの具体的なサービス内容
厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」によると、以下4つの基本活動を複数組み合わせて支援をおこなうことが求められています。
- 自立支援と日常生活の充実のための活動
- 創作活動
- 地域交流の機会の提供
- 余暇の提供
また、利用している子どもだけでなくその保護者に対する支援も重要視されています。それぞれの支援内容に沿って具体例を詳しく見ていきましょう。
自立支援と日常生活の充実のための活動
着替えや食事、時間・持ち物の管理など、日常生活を送るために必要な生活スキルを練習できるようにサポートします。自立支援とは自分一人で生きることではなく、助けが必要な場合は自分で頼めるようになることです。
そのために、放デイでは障害のある子どもが意欲的に取り組める遊びを提供し、楽しみながらスキルを習得していきます。たとえば、買い物ごっこでお金の使い方を知ったり、絵カードを使った視覚的支援で予定を意識したりする活動です。自信をもって挑戦できる環境を整えることで自己肯定感の土台が育ち、子どもたちはすこやかに成長していくことができます。
創作活動
放デイでは工作やゲームなど多彩なプログラムを用意しており、学習とは異なる創造的な学びを深めていきます。創作活動は一人ひとりの感情や個性を表現する貴重な経験です。創作活動の中で心を集中させたり、他の子どもとの交流を深めたりしながら、自分の気持ちを発散させて精神を安定させることができます。創作的な活動を通して自分が何を感じているかを知ることで、自分や他者の気持ちを尊重することができ、協調性やコミュニケーション能力の育成にもつながるでしょう。
放デイでは日常生活の中で身近な自然を感じ、季節の変化に興味を持って活動できるように支援をおこないます。では、具体的な活動の一例を紹介します。
- 散歩
- ピクニック、遠足
- クレヨン、絵の具、粘土などの造形活動
- リズム遊び、リトミック、ダンス
- 歌や楽器の演奏 など
地域交流の機会の提供余暇の提供
他の社会福祉事業やボランティアを積極的に受け入れ、地域の人との交流活動をおこないます。特に発達障害のある子どもは聴覚・視覚過敏だったり、感情のコントロールが苦手だったりすることで、対人・生活の範囲が制限されてしまいがちです。
地域で過ごす時間が少ない環境は子どもにとって必要な経験が減り、心の成長に好ましくありません。自分の住んでいる地域とそこにいる人々を知ることで「自分も地域社会の一員だ!」と自覚することができます。
放デイでは以下のような活動で地域交流の機会を提供しています。
- 地域のイベントへの参加
- 近隣施設とクリスマスなどの合同イベントを開催
- 美術館・博物館・動物園への遠足
- 図書館や児童館などの社会参加活動 など
余暇の提供
放デイでは多種多様な余暇活動を提供しています。決められた活動ではなく子ども自らが選択し、リラックスして好きな時間を楽しめるのが余暇活動です。一人でおこなう運動や手芸だけでなく、友達・職員と一緒に活動するゲームやイベントなどバラエティに富んでいます。普段の学校や家庭ではできない活動が多く、放デイでの経験がよりよい成長へとつなげてくれるでしょう。
具体的な活動例は以下の通りです。
- トランポリン、フラフープ、バランスボール、縄跳びなどの運動遊び
- 絵本
- かるた
- クリスマス会・お正月遊び・七夕・豆まきなど季節のイベント
- リリアン、編み物などの手芸
- ジグソーパズル
- 折り紙
- トランプ、カードゲーム、ボードゲーム
保護者に対する支援
放デイは障害のある子どもだけでなく、その保護者をサポートするための施設でもあります。障害と一口に言っても一人ひとり程度や特性は異なり、保護者だけではなかなか解決の糸口が見つからず、その負担が子どもに悪い影響を及ぼしかねません。
放デイでは保護者に対して子育ての悩みに対する相談や、家庭内での療育についてのペアレント・トレーニングといったバックアップをおこないます。また、放デイに子どもを預けることが保護者のレスパイトにもなり、安心して仕事やリフレッシュができる家族支援の役割にもなるのです。このような支援によって保護者が子どもと向き合うゆとりと自信を回復することで、発達に良い影響を与えることが期待されます。
放デイのプログラム例
放デイは民間企業が運営しているため、施設によってプログラムや療育に特色があります。せっかくなら子どもが興味のある内容で、そこから成長につながる学びを得たいものです。ここでは、放デイが実際におこなっているプログラム例をご紹介します。
- 運動プログラム
- 音楽プログラム
- 学習支援プログラム
- ソーシャルスキルトレーニング
- 英会話
- プログラミング
専門資格を取得しているスタッフがいたり、習い事感覚で通えたりと、施設によって特色が異なります。発達段階やどんなものに興味があるのか、といったポイントで子どもが無理なく通える施設を選ぶのが重要です。放デイは全国に続々と増えているので、まずは実際に足を運んで体験会や見学会に参加してみるとよいでしょう。
「放デイの支援内容は分かったけど、どんな風に過ごすのか想像できない」という保護者の方のために放デイでの1日の流れをご紹介します。施設によって利用時間やプログラム内容は異なりますが、平日と休日の一例を参考にしてみてください。
放デイでの1日の流れ
<平日のスケジュール例>
- 14時~15時:送迎、来所
- 15時:はじめの会、個別活動、集団活動など
- 16時:おやつ、個人活動、個人療育、宿題など
- 17時:おわりの会、送迎、帰宅
平日は学校により多少の違いがありますが、14時から15時頃に施設に到着します。安全性や機能性の観点から、学校・施設・自宅の間を送迎をしてくれる施設が多いです。施設に到着してからは、個人の宿題や創作活動など自由に時間を過ごしたり、集団での運動や公園に出かけたりとさまざまな活動をおこないます。
<休日のスケジュール例>
- 9時:送迎、来所
- 10時:個別活動
- 12時:お昼ご飯
- 13時:集団活動
- 15時:おやつ、自由活動
- 16時:おわりの会、送迎、帰宅
学校休業日でも基本的に内容は変わりませんが、平日では行きにくい工場見学や動物園・美術館などへ出向くこともあります。施設にもよりますが朝9時から10時頃から始まり、帰りの送迎は16時から17時です。
スカウトサービス登録はこちら放デイの利用の流れと料金の目安
放デイを利用するには、まず自治体が発行する受給者証を取得する必要があります。入所したい施設を見つけても、すぐに利用を開始できるわけではありません。ここでは、放デイの利用方法をわかりやすいように4つの手順でご紹介します。スムーズに入所できるよう、以下を参考に手続きを進めてください。
【ステップ1】利用相談
放デイを利用したいと思ったら、まずはお住まいの市役所や区役所など自治体窓口に相談してください。窓口ではどんなサービスを利用したいかなどの聞き取りがおこなわれることもあり、地域にある放デイの情報を教えてもらえることもあります。「放デイを利用したいけれど、どの施設が良いかわからない…」という方も、一度お住まいの自治体の福祉窓口で相談してみてください。
【ステップ2】放デイの施設を見学
気になる放デイが見つかったら、直接施設へ連絡をして見学をします。体験ができるところもあるので、子どもの反応を見つつ、通いたい施設を決めていくのもおすすめです。見学の際は具体的な支援内容を相談し、空き状況の確認や利用料金など詳しく確認しておきましょう。
【ステップ3】通所受給者証を取得
放デイを利用するためには、通所受給者証(受給者証)を取得しなければなりません。受給者証があれば利用料金の1割が自己負担となり、上限金額の超過分は支払わなくて済む仕組みなので、必ず取得しましょう。
受給者証を取得する際に必要な書類は以下の通りです。
- 支援の必要を証明する書類(障がい者手帳や診断書だけでなく、医師意見書)
- 障害児支援利用計画案
- マイナンバーカードや世帯収入がわかる書類など
障害児支援利用計画案は自分で作成することもできますが、市区町村に依頼して聞き取り調査をおこない作成する方法もあります。受給者証の申請から発行には1〜2ヶ月ほどかかるケースもあるので、利用したい施設が決まったら早めに準備しましょう。
【ステップ4】放デイと利用契約・通所開始
申請した書類をもとに調査・審査を経て受給者証の交付がおこなわれたら、いよいよ施設との契約手続きです。受給者証や障害児支援利用計画案といった必要書類を持って施設へ行き、契約の手続きをおこないます。契約後は受給者証に記載された利用開始日より、放デイを利用可能です。
利用料金
放デイは、受給者証があれば1割が自己負担(9割が自治体負担)となります。自治体や事業所によって異なりますが、1回の利用料金は1,000円前後です。
利用料金は、月ごとに利用した日数で計算されます。ただし、世帯収入に応じて月額上限額が定められているので、何回利用しても上限額を超えることはありません。 上限の金額は次の3種類です。
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 非課税世帯(生活保護・低所得など) | 0円 |
| 収入が約920万円以下の世帯 | 4,600円 |
| 収入が約920万円以上の世帯 | 37,200円 |
基本の利用料金のほかにも、おやつ代や食事代、教養娯楽費(遠足・誕生会などイベントで費用が発生する場合)などが発生します。これらの費用は実費で払わなければならないので注意が必要です。放デイによっておやつの内容やイベントの頻度は異なるため、説明会や見学の際に確認しておきましょう。
スカウトサービス登録はこちら放デイの探し方と賢い選び方
放デイは、2012年の法改正で制度化されて以降、毎年事業所数が増加しています。 厚生労働省の資料によると、2025年3月時点で全国に22,859事業所あります。
選択肢が増えている中、お子さんに合った放デイの探し方と選び方がより重要になっています。
放デイの探し方
市区町村の窓口に相談する
お住まいの市区町村の障害福祉課や子ども家庭課、または保健センターなどに相談すると、地域の放課後等デイサービスのリストや、相談支援事業所を紹介してもらえます。相談支援事業所は、お子さんの状況や希望に合った事業所探しをサポートしてくれる専門機関です。
インターネットで検索する
「放課後等デイサービス 〇〇市(お住まいの市区町村名)」で検索すると、多くの情報が見つかります。
「LITALICO発達ナビ」など、障がいのあるお子さんのための施設情報サイトも活用しましょう。これらのサイトでは、プログラム内容、スタッフの専門性、施設の雰囲気、口コミなどが掲載されている場合があります。
病院や地域の相談機関に尋ねる
お子さんが通院している病院や、地域の発達支援センター、児童相談所などで相談し、情報を得ることもできます。
口コミや評判を参考にする
実際に利用している保護者の方の口コミや評判も参考にすると良いでしょう。ただし、あくまで個人の感想なので、最終的にはご自身の目で確かめることが大切です。
気になる事業所が見つかったら、次は見学して希望に合う事業所なのか見極めましょう。
見学で確認すべき10のポイント
見学の際には、事前に何をチェックするか決めてから向かいましょう。チェック項目が決まっていると、複数の事業所を比較検討しやすくなります。
-
支援内容が期待と合致するか
子どもに期待する居場所、勉強、運動、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などの内容が提供されているか、そしてその支援方法や時間の使い方が子どもの特性に合っているかを確認しましょう。 -
送迎の有無と利便性
自宅や学校からの距離、送迎の可否、希望通りの送迎が可能かどうかは、日々の利用において非常に重要です。駐車場の有無も確認しておくと良いでしょう。 -
利用時間と曜日
希望する利用時間や時間帯、週に何回・何曜日に利用できるかを確認してください。祝日や長期休暇時の利用が可能かどうかも、保護者の状況に合わせて確認が必要です。 -
振替や回数変更の柔軟性
急な予定変更があった際に、振替利用や回数変更の融通が利くかどうかは、継続的な利用の上で大切なポイントです。 -
施設内の雰囲気と安全性
照明の明るさ、広さ、音の環境が子どもの好みに合うか、そして安全に遊べる空間が確保されているかを確認しましょう。見学時の子どもの反応も大切な判断材料です。 -
集団活動の規模
集団での活動がメインか、個別支援が中心か。また、大人数での活動か少人数での活動かなど、子どもの特性に合った環境であるかを見極めましょう。 -
利用している子どもの様子
仲良くなれそうなタイプの子がいるか、あるいは苦手なタイプの子がいないかなど、実際に利用している子どもの雰囲気や相性を確認することも重要です。 -
スタッフの対応と人数体制
子どもとの相性はもちろん、スタッフの人数や体制が十分か、入れ替わりの頻度はどうか、保護者との連携がスムーズに取れそうかなど、信頼できるスタッフがいるかを確認してください。 -
保護者との連携体制
利用中の子どもの様子や気になる点について、施設側と密に情報共有し、相談できる体制が整っているかを確認しましょう。親が安心して預けられるかは非常に重要です。 -
子どもの「行きたい」という気持ち
最終的に、子ども自身が「ここに行きたい」と感じるかどうかが、利用の継続と成長にとって最も大切な要素です。見学にはぜひお子さんも一緒に参加し、本人の気持ちを尊重しましょう。
放デイは掛け持ち(複数利用)が可能!
放デイは必ずしも1つの事業所に絞らなくても大丈夫です。近年、様々な特色のある放デイがあるので、複数利用も珍しくありません。平日週5日+不定期で土日もとなると、3ヶ所以上に通わせる方もいます。
また複数事業所の掛け持ちにはメリットがあります。まず1つは様々な人と関われることです。様々なスタッフや他のお子さんと関わることで、お子さんの成長や発達にとって良い機会となることがあります。2つ目はリスク分散です。コロナのクラスターのように急な事情で利用できない場合にもう片方にお願いするなど、いざという時のリスクを分散することができます。
注意点として、自治体によっては、複数施設の利用に制限があったり、条件が設けられたりする場合があります。利用を検討する前に、必ずお住まいの市区町村の担当窓口や児童発達支援センターなどに確認しましょう。
放デイで働くスタッフと仕事内容
放デイは、障害のある子どもたちが安全にかつ適切な支援を受けられるように、人員配置に関する基準が法律で決まっています。主な職種と仕事内容、役割をまとめます。
管理者:各事業所に1名以上
管理者は、事業所全体を管理するポジションです。経営管理や外部機関・施設との調整、スタッフの労務管理、保護者対応などの業務を幅広く担当します。
実は管理者になるために必須の資格はありません。ただ管理者は施設の総合的なまとめ役として、障害児支援に対する知識や経験はもちろん、リーダーシップやマネジメント能力が求められます。
児童発達支援管理責任者(児発管):各事業所に1名以上
児童発達支援管理責任者(以下、児発管)は、利用するお子さんに合わせた個別支援計画を作成・運用する専門職です。保護者とよく話し合って相談支援を実施したり、療育サービスが始まった後も経過をモニタリングしたりして、半年に一度は計画書の見直しをおこないます。
児発管の取得には、一定の実務経験と研修の修了が必要です。実務経験や社会福祉士・介護福祉士など国家資格の有無によっても変わりますが、最低でも5年以上かかります。また、資格の取得後も5年ごとの更新研修の受講が必要です。それだけ専門性を求められる職種といえるでしょう。
児童指導員または保育士:利用定員によって変動
放デイの児童指導員・保育士は、個別支援計画に基づき、遊び・創作活動を通して子どもの療育や指導をおこないます。施設内の清掃やプログラムの準備といった雑務、保護者の相談支援なども児童指導員の仕事です。
保育士と違い「児童指導員」という資格はなく、特定の試験を受ける必要はありません。以下いずれかの要件を満たした場合、「児童指導員任用資格」を取得することができます。
- 幼稚園教諭、または小・中・高のいずれかの教員免許を保有
- 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を保有
- 福祉系職種の専門学校を卒業
- 大学・大学院で社会福祉・心理・教育・社会学系の専門課程を卒業
- 児童福祉施設で2年(中卒の場合は3年)以上の実務経験を持つ者
- 3年以上児童福祉事業に従事し、都道府県知事が適当と認めた者
児童指導員または保育士は、サービス提供時間帯を通じて、以下の人数を配置する必要があります。
- 利用定員10名まで:2名以上
- 利用定員11〜15名: 3名以上
- 利用定員16〜20名::4名以上
- 以降: 利用定員が5人増えるごとに1名ずつ追加
機能訓練担当職員:必要に応じて
機能訓練を行う場合に配置します。放デイにおける機能訓練担当職員の仕事は、日常生活に必要な動作をできる限り一人でおこなえるよう支援することです。
機能訓練担当職員はそれぞれが保有する専門性を活かしながら、一人ひとりに応じた機能訓練計画表を立ててリハビリや療育をおこないます。以下の資格者が働いています。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 公認心理師
- 臨床心理士
看護職員:必要に応じて
医療的ケアを必要とする児童を支援する場合に配置が求められます。放デイの看護職員には、下記いずれかの資格が求められます。
- 看護師
- 准看護師
- 保健師
- 助産師
実際のところ、機能訓練担当職員や看護職員を配置している放デイの数は限られています。多くの事業所では、(1)管理者(2)児童発達支援管理責任者(3)児童指導員または保育士が活躍しています。
スカウトサービス登録はこちら放デイで働くには?無資格でも働ける?
結論から言うと、無資格でも放デイで働くことができます!多くの事業所で、無資格・未経験の方を募集しています。
無資格で働ける職種と役割
無資格の場合、主に指導員(児童指導員補助)や支援員といった立場で働くことになります。具体的な仕事内容は以下の通りです。
- 子どもたちの遊びや活動のサポート
- 学習支援(宿題の手伝いなど)
- 日常生活の指導(自立のサポートなど)
- 送迎業務(普通自動車免許が必要な場合が多いです)
- 事務作業、清掃など
前の章で述べた通り、施設の運営基準上、児童指導員や保育士といった資格を持った職員が一定数配置されている必要があります。そのため、無資格者はあくまでサポート的な役割を担うことが多いです。
働きながら資格取得を目指すことも可能
放デイで実務経験を積むことで、児童指導員任用資格の取得を目指すことができます。例えば、高校卒業後に2年以上児童福祉事業に従事することで、児童指導員任用資格を得られる場合があります。また、働きながら保育士などの資格取得を目指す方も多いです。
求人探しのポイント
無資格の方が放デイの求人を探す場合には、「放課後等デイサービス 無資格」「放課後等デイサービス 未経験」といったキーワードでネットで検索するのがおすすめです。
求人サイトで探す場合には、職種は「児童指導員/指導員」や「支援員」を選択すると募集を見つけやすいです。特に、「未経験者歓迎」「無資格OK」といった記載がある求人に注目してみましょう。
ちなみに医療福祉業界の専門サイトであるコメディカルドットコムは、会員登録なしで求人を見ることができます。具体的な求人のイメージを知りたいという人は是非チェックしてみてください。
放デイに関するよくある質問
最後に、放デイに関するよくある質問を4つピックアップしました。
複数の放デイを利用することはできますか?
複数の放デイを掛け持ちすることは可能です。放デイを利用するために必要な受給者証には支給量(○日/月)が記載されているので、その範囲内であれば利用できます。また、複数の放デイを掛け持ちする場合でも定められた上限金額を超えることはありません。
複数の放デイを利用するメリットは、療育の回数や種類を増やせることです。また、より多くのスタッフや友達との出会いにもつながるでしょう。
放デイは健常児も利用できますか?
基本的に健常児は対象外です。放デイは障害を持つ子どもの居場所や支援の場。利用するためには、療育が必要だと分かる療育手帳、障害者手帳、診断書などが必要となります。
発達障害の診断基準に満たない状態のグレーゾーンの子どもの場合でも、受給者証を取得できれば放デイを利用できます。まずは、お住まいの市町村の障害福祉課や児童発達支援センターに相談してみましょう。
放デイは意味がない?
放デイに意味がないわけではありません。子どもの発達状況や特性に合わせた支援をすることにより、コミュニケーション能力や学習能力が向上します。親子にとっても心の拠り所となる場所となり、仕事が忙しいご家庭でも安心して子どもを預けられるでしょう。
しかし、施設によっては子どもに合った支援を提供できず、子どもが負担に感じてしまうことがあります。放デイを決める際は実際に足を運んで設備の中まで詳しく見学し、子どもと相性が良い施設を見つけることが大切です。
放デイは資格がなくても働けますか?
資格を持っていなくても放デイで働くことは可能です。ただし、前項でご紹介した資格があれば就職や給与面で有利ですし、責任ある仕事を任せてもらえる可能性が高くなります。働きながら取得できる資格もあるので、現場で経験を積みながら支援のプロを目指してみてはいかがでしょう。
スカウトサービス登録はこちらまとめ
放課後等デイサービス(放デイ)は、発達に支援が必要な小学生から高校生が利用できる、いわば「障害のあるお子さんのための学童保育」です。お子さんの自立支援と成長、居場所作り、社会性の育成を主な目的とし、着替えや手洗いなどの生活スキルの向上、創作活動、地域交流、余暇の提供など、多角的な支援を行います。
放デイを利用するには、まずお住まいの自治体窓口に相談し、通所受給者証を取得する必要があります。受給者証があれば、利用料金の1割が自己負担となり、世帯収入に応じた月額上限が設定されるため、安心して利用できます。利用開始前には、施設の見学や体験をおこない、お子さんに合った場所を選ぶことが大切です。
全国に多数存在する放デイの中からお子さんに最適な施設を選ぶには、いくつかのポイントがあります。支援内容が期待と合致しているか、送迎の有無、利用時間や曜日の柔軟性などを確認しましょう。特に重要なのは、施設内の雰囲気や安全性、スタッフの対応、そして何よりもお子さん自身が「行きたい」と感じるかどうかです。複数の施設を掛け持ちし、多様な経験をさせることも可能です。
放デイでは、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、機能訓練担当職員、看護職員といった様々な専門職が活躍しています。無資格・未経験でも「指導員(補助)」や「支援員」として働くことが可能であり、子どもたちの遊びや活動のサポート、学習支援、送迎業務などを担当します。働きながら実務経験を積み、児童指導員任用資格や保育士資格の取得を目指せるなど、キャリアアップの道も開かれています。
事業所からスカウトがくる!
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!