社会福祉士とはどんな仕事?年収、資格の取り方、向いている人など徹底解説
- 更新日
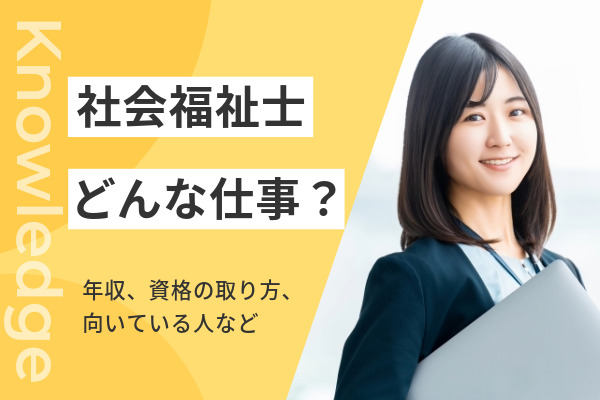
「社会福祉士ってどんな仕事?」
「社会人からでも社会福祉士を目指せる?」
「社会福祉士にキャリアチェンジしたら今よりも年収は上がる?」
このような悩みや疑問はありませんか?
本記事では、社会福祉士の概要や資格の取得方法、仕事内容や給料事情、やりがいや向いている人など総合的に解説します。この記事を読めば、社会福祉士が自分に適した職業なのか、社会人からでも目指すべきか判断できるようになるでしょう。
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!
目次
社会福祉士とはどんな資格?
社会福祉士は、様々な要因で日常生活が困難になっている人々を支援する社会福祉の専門職であり、日本における国家資格です。1987年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」によって、日本で初めての福祉専門職の国家資格として誕生しました。
社会福祉士の呼び名は、英語の職種名であるソーシャルワーカー(Social Worker)や、その略称であるSW、相談員など様々です。病院の場合は医療ソーシャルワーカー、老健の場合は支援相談員など働く場所によっても異なります。
社会福祉士の役割
社会福祉士の役割は、様々な困難や悩みを抱えている方の相談に応じ、適切な社会福祉サービスや関係機関と繋ぐことです。「人と社会をつなぐ専門家」と言えるでしょう。
困難や悩みを抱えている方は、必要なサービスや制度を知らなかったり、金銭的な理由で受けられないといった背景を抱えています。社会福祉士は相談を通じて、置かれている状況やどうなりたいかの希望を整理し、そのニーズを的確に把握した上で助言を行い、適切なサービスの提供をサポートします。
社会福祉士の人数と男女比
社会福祉士の登録者数は、2025年3月末時点で315,589人です。直近のデータによると男女比は、男性が約3割、女性が約7割です。 社会福祉士は女性の割合が高い職業と言えます。
社会福祉士の登録者数は、長年にわたり増加傾向にあります。社会福祉振興・試験センターの資料から直近5年の推移をまとめました。
| 年次 | 登録者数 |
|---|---|
| 2025年3月末 | 315,589人 |
| 2024年3月末 | 299,408人 |
| 2023年3月末 | 280,968人 |
| 2022年3月末 | 266,557人 |
| 2021年3月末 | 257,293人 |
出典:社会福祉振興・試験センター「各年度末の都道府県別登録者数」
社会福祉士と精神保健福祉士の違い
社会福祉士と精神保健福祉士の大きな違いは、支援する対象者です。社会福祉士は身体的、精神的、経済的など様々な理由で日常生活に支障をきたしている方の支援を行います。対象者の幅が広いと言えます。
一方で精神保健福祉士は、心に病や障がいを抱える方を対象とします。精神的な疾患・障がいのある人の支援に特化していると言えるでしょう。さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
社会福祉士になるには?
社会福祉士になるには、受験資格を満たして社会福祉士国家試験に合格することが必須です。国家試験は例年2月に実施されます。年に1度の機会に向けて準備を進める必要があります。
社会福祉士の受験資格
社会福祉士国家試験の受験資格を満たす方法は、学歴と実務経験により12通りあります。社会福祉振興・試験センターのHPで資格取得ルート図が示されています。
ぱっと見では複雑に思えますが、大まかに3つに分類すると理解しやすいです。
(1)すぐに受験できる人
(2)短期養成施設等に通う必要がある人
(3)一般養成施設等に通う必要がある人
詳細な解説は以下の記事で行っています。
社会福祉士の養成施設
社会福祉士の養成施設とは、社会福祉士国家試験の受験資格を得るために必要な知識や技術を学ぶための教育機関です。「短期養成施設」と「一般養成施設」の2種類があり、違いは以下の通りです。
| 項目 | 一般養成施設 | 短期養成施設 |
|---|---|---|
| 対象 | 一般大学・短大卒業者 または相談援助実務経験者 |
福祉系大学・短大卒業者(指定基礎科目履修者) または相談援助実務経験者 |
| 修学期間 | 1年以上(1年~1年半程度) | 6か月以上(約9か月が一般的) |
| 学習形態 | 通学・通信両方あり | 主に通信制、スクーリングは土日中心 |
社会福祉士国家試験の概要、合格率は?
社会福祉士国家試験の概要は以下の通りです。2025年2月2日に行われた第37回社会福祉士国家試験より、新カリキュラムが適用されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 毎年2月頃(年1回実施) |
| 試験科目 | 19科目・129問(新カリキュラム導入後) |
| 試験形式 | 全てマークシート方式(多肢択一) |
| 試験時間 | 午前・午後の2部構成(計約4時間) |
| 合格基準 | 総得点の約60%前後(毎年変動) かつ一部科目での足切りあり |
| 合格発表 | 3月中旬 |
社会福祉士国家試験の合格率は、年度によって変動しますが、近年は上昇傾向にあります。以前は20%台後半から30%台で推移していましたが、直近で合格率は上昇し遂に50%を上回りました。
| 回次 | 合格率 |
|---|---|
| 第37回 | 56.3% |
| 第36回 | 58.1% |
| 第35回 | 44.2% |
| 第34回 | 31.1% |
| 第33回 | 29.3% |
実は社会人から社会福祉士を目指す人は多い!
社会人から社会福祉士を目指す人は多く、なかには60代以上の方も受験しています。第37回社会福祉士国家試験合格発表の結果より、合格者の年齢区分を表にしました。
| 年齢区分 | 合格者数 | 割合 |
|---|---|---|
| ~30歳 | 6,992人 | 44.9% |
| 31~40歳 | 2,616人 | 16.8% |
| 41~50歳 | 3,292人 | 21.2% |
| 51~60歳 | 2,134人 | 13.7% |
| 61歳~ | 527人 | 3.4% |
| 計 | 15,561人 | 100% |
社会福祉士が活躍する主な職場・就職先
令和2年度社会福祉就労状況調査結果によると、社会福祉士の就労先には11分野・50以上の事業所や公的機関が示されており、社会福祉士の活躍先が幅広いことが分かります。
社会福祉士が最も多く活躍している分野は、「高齢者福祉関係」で就労割合は39.3%を占めます。主要な施設・事業所別でみた就労割合は以下の通りです。
| 施設・事業所 | 就労割合 |
|---|---|
| 病院・診療所 | 14.4% |
| 特別養護老人ホーム | 10.0% |
| 障害者支援施設 | 8.0% |
| 地域包括支援センター | 7.5% |
| 市区町村社会福祉協議会 | 6.5% |
| 介護老人保健施設 | 3.4% |
| 児童相談所 | 1.5% |
社会福祉士の仕事内容
社会福祉士の仕事内容は多岐にわたりますが、中心的な業務は相談援助(ケースワーク)と環境調整・連携(コーディネーション)の2つです。
相談援助(ケースワーク)
相談援助は、困りごとを抱える個人や家族に直接寄り添い、問題解決をサポートする社会福祉士の核となる業務です。具体的には以下のステップで進められます。
- 問題の把握とアセスメント:
相談者の話にじっくり耳を傾け、抱えている問題(経済的な困窮、病気や障がいによる生活の困難など)とその背景にある状況を深く理解します。 - 支援計画の策定:
アセスメントに基づき、相談者と一緒に具体的な目標と達成するための支援計画を立てます。どのような公的制度やサービスが必要かを具体的に検討し、最適な道筋を探ります。 - 社会資源の活用と調整:
策定した計画に基づき、相談者のニーズに合った社会資源(例:生活保護などの公的制度、デイサービスや訪問介護といった福祉サービス、地域のNPOやボランティア団体など)を見つけ出し、利用できるよう橋渡しをします。関係機関との連絡調整も行います。 - 支援の実施と評価:
計画に沿って支援を進めながら、定期的に相談者の状況や支援の効果を確認し、必要に応じて計画の見直しを行います。これにより、常に相談者の状況に合わせた柔軟な支援を提供します。
環境調整・連携(コーディネーション)
相談援助だけでなく、相談者を取り巻く環境を整え、多様な関係者と協力することも社会福祉士の重要な役割です。
- 多職種・多機関連携:
相談者の問題を解決するためには、社会福祉士一人では難しいケースも少なくありません。医師、看護師、精神保健福祉士、ケアマネジャー、弁護士、教員、警察など、様々な専門職や機関と密接に連携し、情報共有を行いながらチームとして支援を進めます。 - 地域福祉の推進:
個別の相談援助に加え、地域全体の福祉課題にも目を向けます。地域住民が抱える共通の課題に対し、住民や関係機関と協働して解決策を模索し、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に貢献します。具体的には、福祉に関する広報活動や啓発活動、地域コミュニティの活性化に向けた取り組みなどがあります。
これらの業務を通じて、社会福祉士は相談者一人ひとりの尊厳を尊重し、その人らしい自立した生活を送れるよう、包括的な支援を提供しています。
社会福祉士の年収はどれくらい?
令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査によると、社会福祉士の平均年収は403万円です。福祉の三大国家資格で比較すると、介護福祉士よりも高く、精神保健福祉士と同程度ということが分かります。
| 資格 | 平均年収 |
|---|---|
| 社会福祉士 | 403万円 |
| 精神保健福祉士 | 404万円 |
| 介護福祉士 | 292万円 |
社会福祉士のやりがいと大変さ
社会福祉士の仕事は、人々の生活に深く関わるため、大きなやりがいを感じられる一方で、大変な側面も持ち合わせています。それぞれ見ていきましょう。
社会福祉士のやりがいと魅力
社会福祉士の仕事は、人々の生活を支え、より良い方向へ導くことに大きなやりがいがあります。相談者が抱える問題は多岐にわたりますが、一つひとつに寄り添い、適切な支援や情報を提供することで、感謝の言葉を直接もらえることは何よりの喜びです。
また、行政、医療機関、NPOなど多様な関係機関と連携し、地域全体で課題解決に取り組むダイナミズムも魅力です。支援を必要とする人が孤立せず、安心して暮らせる社会の実現に貢献できる、非常に公共性の高い仕事と言えるでしょう。人との繋がりの中で、自分自身も成長できる奥深さも持ち合わせています。
社会福祉士の大変さと辛いところ
社会福祉士の仕事は、相談者やご家族だけでなく、他職種との直接的な関わりが多く、対人ストレスにさらされやすいです。例えば、相談者本人・家族から焦りや怒りをぶつけられること、医師や看護師との方針や意見の食い違うことが挙げられます。
加えて、業務の多くがワンマン業務として行われるため、抱えるケースを一人で管理し、責任を負うことになります。相談内容が複雑で画一的な対応が難しいため、担当者を変えることも難しいです。この「自分しかいない」状況は、ミスへのプレッシャーや、休みを取りにくいといった形で精神的負担をさらに増大させます。
このような対人ストレスとワンマン業務の複合的な重圧により、社会福祉士はバーンアウト(燃え尽き症候群)しやすいと言われます。
バーンアウトとは、仕事への過度なストレスが長期間続くことによって心身が消耗し、意欲や関心を失ってしまう状態を指します。
医療ソーシャルワーカーの方が、バーンアウトしてしまった経緯をnoteの記事にしていたので紹介します。当事者の言葉が一番リアリティがあります。
若手医療ソーシャルワーカーがバーンアウトするまで
社会福祉士に向いている人
社会福祉士に向いている人の特徴としてよく挙げられるのが、「コミュニケーションが得意・好きな人」です。対利用者・ご家族への相談援助、他職種との連携、関係機関との調整のいずれにもコミュニケーションは欠かせません。
向いていると言うより前提な気がするので、もう少し深掘りして、社会福祉士に向いている人の特徴を3つ紹介します。
他者の変化や成長に喜びを感じられる人
相談者の悩みが解決し、日常生活を取り戻す過程は、まさにその人の成長や変化の現れです。社会福祉士は、その過程を伴走し、支援することで、直接的に人のポジティブな変化に関わることができます。このような変化を間近で見守り、共に喜べる人にやりがいを感じやすいでしょう。
社会全体を良くしたいという志を持つ人
社会福祉士は、個々の相談者の支援を通じて、その人が抱える問題の背景にある社会的な課題に触れる機会が多くあります。例えば、貧困、虐待、差別、孤立といった問題は、個人の努力だけでは解決が難しい場合が多く、社会全体の仕組みや意識の変革が必要となることがあります。個人の支援を通じて社会変革の一端を担うことができる、非常にやりがいのある仕事です。
自分と相手の気持ちや考えをきちんと分けられる人
社会福祉士は、様々な悩みを抱える人の相談に乗りますが、その中で、相手の感情に深く共感するあまり、自分の気持ちと混同してしまうことがあります。また、相手の状況を理解しようとするあまり、自分の価値観や考え方を押し付けてしまう可能性もあります。
社会福祉士は、相手の気持ちに寄り添いながらも、専門家として冷静な視点を持ち、相手の主体性を尊重した支援を行うために、「自分と相手の気持ちや考えをきちんと分ける力」が不可欠なのです。
社会福祉士の需要と将来性
社会福祉士でGoogle検索すると、サジェストに「社会福祉士 やめとけ」という言葉が目に入り、不安に思った方も多いのではないでしょうか。ですがご安心ください、筆者は「社会福祉士は将来性がある」と断言します。順に解説していきます。
「社会福祉士はやめとけ」と言われるのはなぜ?
「社会福祉士はやめとけ」といった声は、主に業務の多忙さ、精神的な負担、そして給与水準への不満から生じることが多いようです。
確かに、社会福祉士の大変さと辛いところで触れたように、複雑な要因からなる対人ストレスと業務負担の存在は否定できません。
しかし、これらの課題は社会福祉士の仕事が持つ本質的な魅力や社会的な必要性を打ち消すものではありません。むしろ、これらの課題が認識され、改善への取り組みが進んでいる点にも注目すべきです。
社会福祉士の需要は高まり続けている
社会全体としては社会福祉士の需要は高まる一方であり、将来的には処遇改善も期待できると筆者は見ています。
まず、日本の社会構造の変化が大きな要因です。少子高齢化の進行は、高齢者福祉、医療福祉の分野で社会福祉士の専門性を必要としています。地域包括ケアシステムの推進により、住み慣れた地域で生活を続けるための包括的な支援が求められており、その中心的な役割を担うのが社会福祉士です。
また少子化に関わる児童・母子福祉関係について、2023年4月1日に「こども家庭庁」が新たに設置され、「こども家庭ソーシャルワーカー」という新しい資格が生まれました。社会福祉士からの取得ルートがあることから、この分野にもっと社会福祉士を集めたいという思惑があるのでしょう。
国や自治体による福祉施策の強化と法整備の進展も、社会福祉士の需要を後押ししています。例えば、医療機関における入退院支援、学校におけるスクールソーシャルワーカーの配置拡大、成年後見制度の利用促進など、社会福祉士の専門性を活かせる場は広がり続けています。
まとめ
社会福祉士は、日常生活に困難を抱える人々を支援する国家資格を持つ専門職です。相談者の状況を把握し、適切な社会福祉サービスや関係機関へ繋ぐ「人と社会をつなぐ専門家」として、その役割は多岐にわたります。登録者数は増加傾向にあり、2025年3月末時点で315,589人、約7割が女性です。
社会福祉士になるには、国家試験の合格が必須で、受験資格は学歴や実務経験により異なります。国家試験の合格率は近年上昇傾向にあり、50%を超えることもあります。
社会福祉士の就職先は高齢者福祉、医療、障がい者支援など多岐にわたり、最も多いのは高齢者福祉分野です。仕事内容は、相談者への個別支援(ケースワーク)と、多職種・多機関との連携による環境調整(コーディネーション)が中心です。平均年収は約403万円で、精神保健福祉士と同程度です。
対人ストレスやワンマン業務による精神的負担が大きい側面から「社会福祉士はやめとけ」という声もありますが、人からの感謝や社会貢献を実感できるやりがいがあります。少子高齢化や福祉施策の強化により、社会福祉士の需要は高まっており、将来的には処遇改善も期待できる将来性のある職業と言えます。
事業所からスカウトがくる!
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!









