特養の管理栄養士とは?仕事内容や給与相場、やりがいなどを紹介
- 更新日
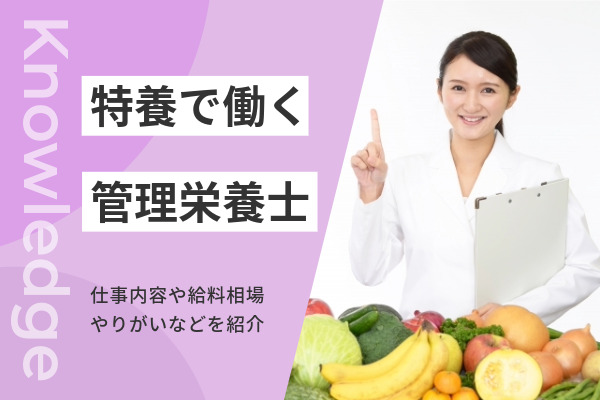
特別養護老人ホームは、管理栄養士が活躍できる職場の一つです。
しかし、なかには特養での仕事内容や給料相場がわからず、就職・転職するかどうかを迷っている管理栄養士の方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、特別養護老人ホームにおける管理栄養士の仕事内容、給与相場、やりがいについてご紹介しますので、特別養護老人ホームへの就職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!
目次
特別養護老人ホーム(特養)とは?
特養とは、介護保険サービスが適用される公的施設の1つで、原則として要介護3以上の認定を受けた方が入所できます。
介護を必要とする方のために、「終の棲家」となる生活の場と24時間の介護サービスの提供を目的としており、認知症の方の受け入れも可能です。
特養の入所の対象者
- 介護保険の要介護認定で「要介護3」以上の認定を受けた65歳以上の方
- 40~64歳の特定疾患がある要介護3以上の方
- 特例で認められた要介護1、2の方
特養のサービス内容とは?
特養では、自宅での生活が困難な高齢者に対して、介護だけでなく、食事の提供、健康管理、療養上の世話、機能訓練、相談援助など、生活全般にわたる支援を行います。
そのため、医師、看護職員、介護支援専門員、介護職員、機能訓練指導員、管理栄養士・栄養士、生活相談員など様々な職種の方が働いています。
特養で働く管理栄養士の仕事内容は?
特養で働く管理栄養士は、入居者の皆様の健康を食の面から支える重要な役割を担っています。単に食事を提供するだけでなく、栄養ケアマネジメントや衛生管理、行事食の企画など、業務内容は多岐にわたります。多職種との連携も欠かせず、チームの一員として入居者の方々の生活を豊かにする仕事です。ここでは、特養で働く管理栄養士の具体的な仕事内容について詳しく解説していきます。
食事の提供
特養における食事の提供は、単に栄養を摂取するだけでなく、入居者の方々にとって大きな楽しみの一つです。管理栄養士は、栄養バランスだけでなく、季節感や彩り、食べやすさにも配慮した献立を作成します。個々の入居者の嚥下機能やアレルギー、嗜好などを考慮し、必要に応じて食事形態の変更や個別対応も行います。また、冷蔵庫や冷凍庫などの食材を定期的にチェックして在庫管理を行いながら、過不足がないように食材発注をするのも業務の一つです。
栄養ケアマネジメント
入居者一人ひとりの栄養状態(体重、血液検査データ等)、食事の摂取状況、運動量、さらに嗜好、アレルギー、食事の形態といった情報を把握し、個別の栄養ケア計画を作成します。作成後は定期的な栄養評価を実施し、必要に応じて栄養指導や栄養補助食品の提供を行います。
特に、低栄養や嚥下障害のリスクがある入居者に対しては、食事中の様子を直接確認するミールラウンドを行い、嚥下や咀嚼の状態を把握します。
また、入居者の意向を把握するためのアンケート調査を行うこともあります。
衛生管理
特養の管理栄養士は、入居者に安全な食事を提供するため、調理場や配膳の衛生管理を徹底し、体制を整備します。具体的には、厨房やキッチンでの衛生管理指導やマニュアル作成などが業務に含まれます。
施設で食事を提供する際には、食品衛生責任者の配置が法律で義務付けられていますが、管理栄養士の資格があれば、食品衛生責任者の資格を持っていなくてもその業務を担うことができます。
衛生管理は、入居者の健康維持に直接関わる非常に重要な業務です。
行事食やイベント食の企画・実施
毎日の献立作成に加え、季節を感じるイベント食や誕生日といった特別な日の食事の企画・実施を行うのも管理栄養士の大切な業務の一つです。そのために、行事食やイベント食の献立作成から食材の手配、調理の指示までを担当します。イベント食や行事食を実施することで、季節感を味わったり、食欲が増進したりするなど、入居者の生活向上に繋がります。
多職種連携
特養では、医師、看護師、介護職員、リハビリスタッフなど、様々な職種の方が働いています。管理栄養士は、それぞれの専門職と連携し、入居者の方々の情報を共有しながら、チームとしてケアを行います。栄養に関する専門的な知識や意見を共有し、入居者の方々にとって最適なケアを提供します。
栄養マネジメント加算等の管理
特養では、栄養管理に関する様々な加算制度があります。管理栄養士は、これらの加算を取得するために必要な書類作成や記録管理を行います。適切な栄養管理を行うことで、入居者の方々の健康状態の改善や維持に貢献するとともに、施設の運営にも貢献しています。
特養で働く管理栄養士の1日の流れ(例)
08:30 出勤、朝礼
他の職員と情報共有を行い、入居者の体調や食事に関する申し送り事項を確認します。夜間の状況や、当日の予定などを把握し、スムーズに業務に入れるように準備します。
09:00 朝食の準備、提供
朝食の時間に合わせて、食事の準備を行います。献立の確認や配膳、食事介助などを行います。入居者の方々の食事の様子を観察し、食欲や摂取量、嚥下状態などを確認します。必要に応じて、食事形態の変更や個別対応を行います。
10:00 午前の業務
午前の業務は、栄養ケアマネジメントが中心となります。入居者一人ひとりの栄養状態を評価し、栄養ケア計画を作成・実施します。定期的な栄養評価や、必要に応じた栄養指導を行います。また、医師や看護師、介護職員など、多職種と連携し、入居者の栄養に関する情報を共有します。
12:00 昼食の準備、提供
昼食の時間に合わせて、食事の準備を行います。献立の確認や配膳、食事介助などを行います。入居者の方々の食事の様子を観察し、食欲や摂取量、嚥下状態などを確認します。必要に応じて、食事形態の変更や個別対応を行います。
13:00 休憩
昼休憩を取ります。
14:00 午後の業務
午後の業務は、事務作業や会議、行事食の企画など、多岐にわたります。栄養ケア計画の作成や記録、書類作成などを行います。また、多職種との会議に参加し、入居者の栄養に関する情報を共有します。行事食やイベント食の企画・準備も行います。
17:00 夕食の準備、提供
夕食の時間に合わせて、食事の準備を行います。献立の確認や配膳、食事介助などを行います。入居者の方々の食事の様子を観察し、食欲や摂取量、嚥下状態などを確認します。必要に応じて、食事形態の変更や個別対応を行います。
18:00 終礼、記録
1日の業務終了後、終礼を行います。その日の業務内容や入居者の状況などを報告し、情報共有を行います。記録を作成し、翌日の業務に備えます。
※補足
上記はあくまで一例であり、施設によっては勤務時間や業務内容が異なる場合があります。
特養の管理栄養士は、入居者の栄養管理だけでなく、食に関する様々な業務を担当します。
多職種との連携が非常に重要であり、チームの一員として入居者を支える役割を担っています。
特養で働く管理栄養士の給料相場
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護施設で働く管理栄養士・栄養士の平均年収はおよそ380万円(ボーナスも含みます)となっています。
専門性を高めることも給料アップにつながります。例えば、高齢者ケアに関する専門資格を取得したり、学会発表や研修会への参加を通じて知識やスキルを向上させたりすることで、施設からの評価が高まり、給与アップにつながる可能性があります。
高齢化が進む現代において、介護施設、特に特養における栄養管理の重要性はますます高まっており、管理栄養士の専門知識とスキルへの需要は今後さらに増加することが予想されます。このような背景から、今後も介護業界における管理栄養士の給料水準は上昇傾向を維持、あるいはさらに高まることが期待されています。
ただし、個々の施設の経営状況や人事制度によって給与体系は異なるため、就職や転職を検討する際には、詳細な条件を確認することが重要です。
特養の管理栄養士のやりがいとは?
特養の管理栄養士の大きなやりがいは、入居者の方々から直接「おいしい」と言っていただけることです。日々の献立作成から、栄養状態のアセスメント、個別の栄養指導、そして安全な食事提供のための衛生管理、さらには季節感あふれるイベント食の企画・実施まで、多岐にわたる業務を通して入居者の方々の生活を支えている実感があるからこそ、「おいしい」の一言は、何よりも大きな喜びと達成感につながります。
管理栄養士は、単に栄養バランスを考慮した献立を作成するだけでなく、入居者一人ひとりの嗜好や健康状態、嚥下機能などを詳細に把握し、それぞれのニーズに合わせた食事を提供することが求められます。きめ細やかな栄養ケア計画に基づいた食事は、入居者の健康維持・改善に大きく貢献します。
また、管理栄養士の専門知識を活かした栄養指導を通して、入居者の体調が目に見えて回復したり、食事を通じて健康をサポートできたりすることも、この仕事ならではのやりがいです。食欲不振だった方が食事をしっかりとれるようになったり、栄養状態の改善が見られたりすることは、管理栄養士としての専門性を活かせている証であり、大きなモチベーションとなります。入居者の笑顔と健康を支えることができるという実感が、日々の業務への活力となるのです。
特養の管理栄養士の大変な部分は?
特養の管理栄養士は、入居者の食事と健康を支える重要な役割を担っています。多くの施設で配置される管理栄養士は一人であるため、業務量が多く、困難に感じる場面も少なくありません。他職種との連携においては、意見の相違から人間関係のストレスが生じることもあります。また、入居者が食事が摂れなくなり、最期を迎える際には、無力感や辛さを感じることもあるでしょう。
このように、特養の管理栄養士の仕事は決して容易ではありません。しかし、入居者の健康状態が改善したり、笑顔を見られたときには、大きなやりがいを得られます。特養の管理栄養士を目指すかどうかは、仕事の大変さとやりがいを理解した上で検討することが大切です。
特養での勤務が向いている管理栄養士の特徴は?
特養での勤務は、次のような方に向いていると言われます。
利用者と直接関わりたい方
特養は、他の介護施設と異なり、入居者にとって「終の棲家」となる場所です。そのため、管理栄養士は食事の提供だけでなく、入居者の生活全般にわたる支援を行います。長期的な栄養管理を行う中で、利用者の方の健康状態が改善していく様子を間近で見守ることができるのは、特養の管理栄養士ならではの喜びです。また、利用者の食事の様子や栄養状態を長期的に見守り、直接的なコミュニケーションを取りながら確認できることも特養の管理栄養士の魅力です。
コミュニケーション能力が高い方
特養の管理栄養士は、多職種のスタッフと連携しながら業務を進める必要があり、協調性が重要です。また、利用者の健康状態を把握し、食事の提供や栄養指導を行うためには、高いコミュニケーション能力が求められます。
イベントを企画・運営するのが好きな方
特養では、利用者の方々に食事を楽しんでいただくため、行事食やイベント食といった特別な食事が企画・提供されます。例えば、クリスマス、お正月、ひな祭りなどに合わせた食事がこれにあたります。自身のアイデアが料理に活かされ、普段以上に楽しんで食事をする利用者の方々の様子を見ることは、管理栄養士にとって大きなやりがいとなるでしょう。
特養の管理栄養士になるためには?
特養の管理栄養士になるためには、栄養士の資格取得に加えて、高齢者福祉や介護に関する知識、そして何よりも利用者の健康を第一に考える熱意が求められます。
栄養士養成課程のある大学や専門学校を卒業後、国家試験に合格することで栄養士資格が得られます。その後、管理栄養士の国家試験を受験し合格することで、より専門性の高い管理栄養士として働く道が開かれます。
特養では、利用者の個々の身体状況や嚥下能力に合わせた食事の提供、栄養ケア計画の作成、多職種との連携、食を通じた生活の質の向上など、多岐にわたる業務を担当します。これらの業務を遂行するためには、栄養学の知識だけでなく、コミュニケーション能力やチームワークも非常に重要になります。また、高齢者の栄養状態は日々変化するため、常に新しい知識や情報を学び続ける姿勢も大切です。
特養の管理栄養士の勉強方法
特養の管理栄養士は、高齢者の栄養管理において専門的な知識と技術が求められる重要な職務です。通常の管理栄養士国家試験で問われる知識に加え、特養では認知症、脳血管疾患、高次機能障害といった病態や、摂食嚥下障害など、より専門性の高い知識と理解が不可欠となります。そのため、特養の管理栄養士として働くには、これらの専門分野について深く学ぶことが重要となります。
特養の目的を理解する
特養の管理栄養士は、医療機関での経験が長いほど、求められる役割の違いに戸惑うことがあるかもしれません。医療機関では治療に合わせた栄養管理が重視されますが、特養では生活に寄り添った栄養管理が重要となるため、施設の特徴を理解しておくことが大切です。
特養の管理栄養士の志望動機
特養の管理栄養士の志望動機を伝える際には、特養で働くことへの熱意が伝わるように、以下の点を意識しましょう。
- 特養の仕事内容を具体的に理解していることを示しましょう。
- 特養での勤務を通して、管理栄養士としてやりがいを感じ、自身のスキルアップを目指したいという意欲を伝えましょう。
- これまでの経験や管理栄養士を目指した理由を述べましょう。
- 具体的なエピソードを交えることで、説得力を高めましょう。
- 施設の理念や取り組みへの共感を明確に伝えましょう。
特養の管理栄養士におすすめの関連資格
特養で働く管理栄養士にとって、資格の取得が勤務に役立つこともあります。資格取得を目指すのであれば、「NST専門療法士(栄養サポートチーム専門療法士)」と「介護食士」の2つがおすすめです。
NST専門療法士(栄養サポートチーム専門療法士)
NST専門療法士とは、日本臨床栄養代謝学会が認定する資格で、栄養サポートチーム(NST)の一員として、低栄養状態の患者さんや重症患者さんの栄養管理を行う専門職です。管理栄養士の他に看護師、薬剤師なども取得できます。
病院で発展したNSTですが、近年では特養でも低栄養改善や褥瘡(じょくそう)予防、看取りケアなどにおいてNSTの考え方を取り入れる施設が増えています。NST専門療法士の資格を持つことで、多職種と連携し、より専門的な視点から利用者の栄養状態を改善するための計画立案や介入に貢献できます。特に、長期的な視点で栄養管理を行う特養において、その専門性は高く評価されます。
介護食士
介護食士とは、要介護者への食事提供に関する専門知識・技術を持つ人に交付される民間資格です。1級から3級まであり、調理訓練校や調理師学校などで講習会を受講後、修了試験に合格することで取得できます。
3級は受講資格がなく、受講時間も72時間と十分に確保されているため、介護食の基礎を学ぶのに適しています。より専門的な知識を習得し、管理栄養士としてのスキルアップを目指す場合は、2級や1級の受講が良いでしょう。
介護関連の資格を取得していると、キャリアアップや待遇面においても有利に働く場合があります。今後、介護の分野でキャリアを形成しようと思っている管理栄養士の方は、ぜひ資格取得を検討してみてください。
まとめ
特養は、要介護3以上の方が入所する施設であり、管理栄養士が活躍する場所の一つです。特養の管理栄養士の仕事は、高齢者の健康を食事の面からサポートする、社会貢献度の高い業務です。入居者やその家族から感謝されることも多く、また、多職種と連携しながらチーム医療の一員として活躍できるというやりがいもあります。
もちろん、入居者の状態に合わせた食事の提供や栄養管理、衛生管理など、責任のある業務も多く、仕事は決して楽ではありません。しかし、その分大きな達成感を得られるでしょう。
高齢化が進む現代において、介護施設、特に特養における栄養管理の重要性は増しており、管理栄養士の専門知識とスキルへのニーズは今後ますます高まると予想されます。就職先の選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
事業所からスカウトがくる!
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!










