ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?仕事内容から年収、資格取得方法まで徹底解説
- 更新日
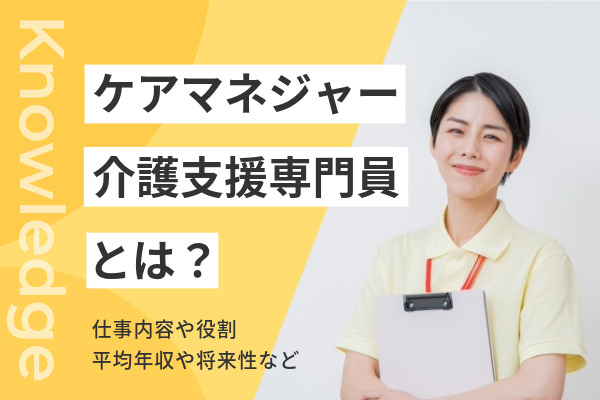
高齢化が進む日本で、ますます重要性が増すケアマネジャー(介護支援専門員)。その役割は多岐にわたり、介護を必要とする人々の生活を支える上で欠かせない存在です。
この記事では、ケアマネジャーの仕事の基本から、勤務先による役割の違い、気になる給料や働き方まで、包括的に解説します。すでにケアマネジャーとして活躍している方も、これから目指す方も、改めてこの仕事の奥深さを知るきっかけになるでしょう。
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!
目次
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
ケアマネジャーは、介護支援専門員という公的資格を持つ専門職です。介護を必要とする高齢者やその家族が、適切な介護サービスを受けられるよう支援する役割を担います。具体的には、一人ひとりの心身の状況や生活環境、希望に沿った「ケアプラン」を作成し、介護サービス事業所や医療機関などとの連携・調整を行います。介護保険制度におけるサービスの入り口として、利用者と介護サービスをつなぐ重要な存在です。
なお、「ケアマネジャー」と「ケアマネージャー」のどちらの表記が正しいかという疑問を持つ方がいますが、厚生労働省や公的な文書では「ケアマネジャー」と表記されることが一般的です。正式な資格名も「介護支援専門員」であり、「ケアマネジャー」は通称として広く使われています。
スカウトサービス登録はこちらケアマネージャーの仕事内容とは?
ケアマネジャーは、要介護者やその家族が安心して生活できるよう、さまざまな角度からサポートします。その仕事は多岐にわたりますが、ここでは主な流れに沿って解説します。
- インテーク
- アセスメント
- ケアプラン作成
- サービス調整
- 実施・モニタリング
- 介護保険関連の事務
インテーク
インテークとは、介護の相談を初めて受ける際の面談のことです。利用者の状況や家族構成、生活環境、そしてどのようなことで困っているのか、どんな生活を送りたいのかといった希望を丁寧にヒアリングします。この段階で、利用者やご家族との信頼関係を築くことが何よりも大切になります。
アセスメント
インテークで得た情報をもとに、利用者の課題やニーズを分析する作業がアセスメントです。具体的には、利用者の自宅を訪問し、身体状況や住まいの環境、ご家族の状況などを詳細に把握します。この際、単に情報を集めるだけでなく、利用者が「できること」にも目を向け、自立した生活を送るための可能性を探ります。
ケアプラン作成
アセスメントの結果をもとに、利用者一人ひとりに合った「ケアプラン」を作成します。ケアプランは、どのようなサービスを、どれくらいの頻度で、誰が提供するのかを具体的に定めた計画書です。この計画は、利用者やご家族の意向を最大限に尊重しながら、自立支援を目的として作成されます。
ケアプランとは、正式には「介護サービス計画書」といい、介護保険サービスを利用するうえで欠かせない、利用者一人ひとりのための計画書です。
具体的には、利用者の心身の状況や生活環境、そして「どんな生活を送りたいか」という希望をもとに、どのような介護サービスを、どのくらいの頻度で、どのように利用するかを具体的にまとめたものです。
サービス調整
ケアプランに沿って、必要な介護サービス事業所や医療機関などと連携・調整を行います。訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなど、さまざまなサービス提供者と連絡を取り合い、利用者にとって最適なサービスが開始できるように手配します。
実施・モニタリング
ケアプランがスタートした後は、サービスが適切に提供されているかを確認するモニタリングを行います。定期的に利用者宅を訪問したり、電話で状況を確認したりして、利用者の状態やサービスの満足度を把握します。もし、状況に変化があれば、必要に応じてケアプランの見直しを行います。
介護保険関連の事務
ケアマネジャーは、利用者やご家族に代わって、介護保険の申請や更新手続きを代行することもあります。また、毎月のサービス利用実績を管理し、介護報酬の請求に必要な書類を作成するといった事務作業も重要な仕事の一つです。これらの業務を通じて、介護保険制度の円滑な運用を支えています。
スカウトサービス登録はこちら【勤務先別に解説】ケアマネジャーの役割
ケアマネジャーは、働く場所によってその役割や仕事内容が少しずつ異なります。ここでは、主な勤務先別に、それぞれのケアマネジャーがどのような役割を担っているか解説します。
居宅介護支援事業所
「居宅ケアマネ」とも呼ばれ、在宅で生活する高齢者をサポートするのが主な役割です。利用者一人ひとりの自宅を訪問し、アセスメントやケアプランの作成、サービス事業者との調整を行います。最も利用者と密接に関わる働き方であり、地域の医療機関や行政とも連携して、在宅生活を継続できるよう包括的に支援します。
介護施設
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの介護施設で働く「施設ケアマネ」は、入居者のケアプランを作成するのが主な仕事です。居宅ケアマネとは異なり、利用者と日常的に顔を合わせるため、日々の体調や様子を把握しやすいのが特徴です。施設内の多職種(介護士、看護師、機能訓練指導員など)と連携し、より専門的で一貫したケアを提供します。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、地域の住民を幅広く支援しています。ここで働くケアマネジャーは、介護予防ケアプランの作成や、介護に関する総合的な相談業務を担います。介護保険の利用が必要になる前の段階から関わり、高齢者が地域で安心して暮らせるよう、医療、福祉、保健の専門家と協力してサポートします。
小規模多機能型居宅介護
「小規模多機能」は、通い・泊まり・訪問のサービスを組み合わせて提供する事業所です。この施設で働くケアマネジャーは、事業所の利用者に限定したケアプランを作成します。利用者と常に同じ場所で過ごす時間が多いため、その方の変化に素早く気づき、よりきめ細やかなサポートを提供できるのが特徴です。
自治体の役所
自治体の役所で働くケアマネジャーは、介護保険の運営に関わる事務業務や、地域のケアマネジャーの指導・監査を行います。また、地域の実情に応じた介護サービスの整備計画を策定するなど、より広域的な視点で介護保険制度を支える役割を担っています。利用者と直接関わる機会は少ないですが、日本の介護保険制度を裏側から支える重要な存在です。
スカウトサービス登録はこちらケアマネジャーの働き方・1日の流れを解説
ケアマネジャーの働き方は、勤務先によって大きく異なります。ここでは、居宅介護支援事業所に勤務する居宅ケアマネと、施設に勤務する施設ケアマネの1日の流れを比較して見ていきましょう。
居宅ケアマネの1日の流れ
居宅ケアマネは、利用者さんのご自宅を訪問することが多いため、外出とデスクワークをバランスよく組み合わせた働き方になります。
| 09 : 00 | 出勤・ミーティング | メールや留守番電話の確認、今日のスケジュールや利用者に関する情報共有を行います。 |
| 10 : 00 | 利用者宅訪問(モニタリング) | 利用者宅を訪問し、体調や介護サービスの利用状況を確認します。困りごとや今後の生活への意向などを丁寧に聞き取ります。 |
| 12 : 00 | 休憩・昼食 | 訪問の合間に昼食をとります。移動時間や次の予定によっては、ゆっくり取れないこともあります。 |
| 13 : 00 | サービス担当者会議 | 新規または既存の利用者について、本人や家族、サービス事業所の担当者(ヘルパー、看護師など)が集まり、ケアプランの内容を協議します。 |
| 15 : 00 | 事務作業・連絡調整 | 事務所に戻り、訪問で得た情報を記録したり、ケアプランを作成・修正したりします。病院のソーシャルワーカーや他の事業所と電話で連絡を取り合います。 |
| 17 : 00 | 給付管理業務 | 利用者のサービス利用実績を確認し、介護保険の給付管理(介護報酬の請求)を行います。月末にかけて特に忙しくなります。 |
| 18 : 00 | 退勤 | 一日の業務を終え、退勤します。緊急の連絡が入ることもあるため、オンコール体制をとっている事業所もあります。 |
- 利用者さんやご家族とのコミュニケーションが中心で、信頼関係を築くことが大切です。
- 外出が多いため、スケジュール管理能力が求められます。
- 急な相談や対応が必要になることもあり、柔軟な対応力が重要です。
施設ケアマネの1日の流れ
施設ケアマネは、基本的に施設内で業務を行うため、居宅ケアマネに比べて外出は少なくなります。入居者さんと顔を合わせる機会が多く、他の職種のスタッフとの連携が不可欠です。
| 09 : 00 | 出勤・申し送り | 朝礼や夜勤スタッフからの申し送りを受け、利用者の夜間の様子や体調の変化について情報共有します。 |
| 10 : 00 | 利用者との面談・モニタリング | 施設内の居室を訪れ、利用者と直接話をしたり、介護スタッフから普段の様子を聞き取ったりします。 |
| 12 : 00 | 昼食 | 利用者の食事介助を兼ねて、昼食をとることもあります。 |
| 13 : 00 | ケアプラン作成・書類整理 | 事務室で、アセスメントやモニタリングで得た情報をもとにケアプランを作成・修正します。 |
| 15 : 00 | サービス担当者会議 | 施設内の会議室で、利用者や家族、施設の介護・看護スタッフなどが集まり、ケアプランを協議します。 |
| 16 : 00 | 多職種連携・事務作業 | 施設の看護師やリハビリスタッフと情報交換をしたり、入所希望者やその家族の対応をしたりします。 |
| 18 : 00 | 退勤 | 一日の業務を終え、次の勤務者へ申し送りを行い、退勤します。 |
- 担当する入居者さんの状況を、日常的に細かく把握しやすい環境です。
- 施設内の多職種との連携が非常に重要で、チームワークが求められます。
- 外部との連絡調整は少なく、施設内の業務に集中できます。
ケアマネジャーの給与事情
厚生労働省が公表している「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、ケアマネージャーの平均年収は450万円程度です。常勤ケアマネージャーの月給相場を、令和5年と令和6年の情報と比較してみていきましょう。
【常勤のケアマネージャー(介護支援専門員)】
令和5年12月 |
令和6年12月 |
|
平均給与額(賞与や手当含む) |
363,760円 |
375,410円 |
平均年収 |
4,365,120円 |
4,504,920円 |
上記を比較すると、1年で約1.1万円程度平均給与額が上がっています。これは、業務手当や資格手当などの平均手当額が上がったことが要因です。では次に、常勤介護職員と比較して見ていきましょう。
【常勤の介護職員】
令和5年12月 |
令和6年12月 |
|
平均給与額(賞与や手当含む) |
324,240円 |
338,200円 |
平均年収 |
3,890,880円 |
4,058,400円 |
介護職員の平均給与額と比較すると、3.7万円程度の差があります。そのため、ケアマネージャー資格を取得することで、大幅な給与アップが期待できるでしょう。また、少子高齢化による福祉従事者の人材ニーズにより、今後もケアマネージャーの給与は上がっていくと予想されています。
スカウトサービス登録はこちらケアマネジャーになるには?
ケアマネジャー(介護支援専門員)になるためには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を終了する必要があります。資格取得までの流れを解説します。
5年以上の実務経験を積み受験資格を満たす
ケアマネージャーになるには、指定された業務に通算5年以上従事している必要があります。具体的には以下のいずれか2つです。
- 介護福祉士や社会福祉士など、特定の国家資格に基づく業務に通算5年(かつ900日以上)従事している
- 生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員として、受験資格に定められている業務に通算5年(かつ900日以上)従事している
「特定の国家資格」には以下が挙げられます。
| 特定の国家資格 |
|---|
| 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士 |
従事期間は試験日の前日までカウントされます。ケアマネ試験の申し込み時点で実務経験が足りていない場合でも、「実務経験見込証明書」を提出すれば受験可能です。
介護支援専門員実務研修受験試験に合格する
受験資格を満たした上で、都道府県が実施する「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する必要があります。試験は年1回実施されます。
介護支援専門員実務研修を終了する
試験合格後は、各都道府県が実施する「介護支援専門員実務研修」を受講し、修了する必要があります。実務研修では、ケアプラン作成などに関する講義・演習(87時間以上)と、居宅介護支援事業所での原則3日間の実習が必要です。
介護支援専門員資格登録簿に登録する
実務研修を修了した後は、各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」に登録します。この登録により、介護支援専門員として認められます。
介護支援専門員証の交付を受ける
登録後、都道府県知事から「介護支援専門員証」の交付を受けます。この証を持つことで、晴れてケアマネジャーとして業務を行うことができます。
5年ごとに更新研修を受ける
ケアマネジャーの資格には有効期限があり、5年ごとに「介護支援専門員証更新研修」を受講し、更新手続きを行う必要があります。この研修は、最新の介護保険制度や専門知識を学び、質の高いケアマネジメントを維持するために義務付けられています。
スカウトサービス登録はこちら試験の概要と合格率
先述した通り、ケアマネージャーになるためには、介護支援専門員研修受講試験に合格しなければなりません。試験は年に1回実施されており、毎年10月頃に行われます。
試験形式
試験は、マークシート方式の五肢複択式で、5つの選択肢から複数の正答を選ぶ形式です。試験時間は120分で、問題数は計60問出題されます。
出題分野
出題分野は以下の2つに分かれています。
- 介護支援分野(25問): 介護保険制度の基礎知識、要介護認定、居宅サービス計画・施設サービス計画の基礎知識など。
- 保健医療福祉サービス分野(35問): 保健医療サービスや福祉サービスに関する知識、疾病や障害に関する基礎知識、介護技術など。
合格基準
合格基準は、各分野で正答率70%以上が目安とされています。しかし、試験の難易度によって合格基準点は補正されるため、毎年変動します。どちらか一方の分野でも基準点を満たせない場合は、合計点が高くても不合格となります。
合格率と試験難易度
ケアマネジャー試験の合格率は、例年10〜20%前後で推移しており、他の福祉系国家資格と比較して低めです。受験資格の厳格さや、五肢複択式の出題形式、そして各分野で基準点を満たす必要があるため、難易度は高いと言えます。
令和3年~令和6年までの合格率をまとめました。
| 全国の合格率 | |
|---|---|
| 令和3年 | 23.3% |
| 令和4年 | 19.0% |
| 令和5年 | 21.0% |
| 令和6年 | 32.1% |
| 4年間の平均 | 23.8% |
令和6年の試験では合格率が32.1%となり、過去最高を記録しました。合格率は年度によって変動するため、事前の対策は必須となります。
出典:厚生労働省|「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」
スカウトサービス登録はこちらケアマネジャーのやりがい・大変なこと・向いているタイプ
ケアマネジャーの仕事には、専門性や社会貢献性の高さからくるやりがいがある一方で、精神的・肉体的な負担も伴います。
やりがい
利用者や家族からの感謝適切なケアプランを作成し、サービスの調整をすることで、利用者やその家族の生活の質の向上に貢献できます。直接「ありがとう」と言われることが大きなモチベーションになります。
専門性の高さとスキルアップ医療、福祉、介護保険制度など幅広い知識が求められるため、常に学習を続けることで専門性を高められます。キャリアパスが明確であり、主任ケアマネジャーなどへのステップアップも可能です。
社会貢献性の高い仕事高齢化社会において、利用者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することは、社会全体に大きく貢献できる仕事です。
大変なこと
多岐にわたる業務と責任ケアプラン作成だけでなく、関係機関との連携、書類作成、利用者や家族からの相談対応など、業務範囲が広く、責任も重いです。
精神的な負担利用者の病状悪化や、家族との関係調整、時には看取りに立ち会うなど、精神的に辛い場面に直面することもあります。
時間管理の難しさ複数の利用者を担当するため、それぞれの状況に合わせて訪問や会議のスケジュールを調整する必要があり、時間管理が難しい場合があります。
向いているタイプ
コミュニケーション能力が高い人利用者、家族、医療機関、サービス事業所など、多くの人と関わるため、相手の気持ちを汲み取り、円滑な人間関係を築けることが重要です。
責任感が強く、冷静な判断ができる人利用者の生活全体を支える役割を担うため、責任感が求められます。また、緊急時や困難な状況でも、冷静に状況を判断し、適切な対応をとれることが大切です。
学習意欲が高く、探究心がある人介護保険制度は頻繁に改正され、新たな情報やサービスも出てくるため、常に学び続ける姿勢が必要です。より良いケアを追求できる探究心も重要となります。
スカウトサービス登録はこちらケアマネジャーの将来性
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、将来性が非常に高い職業です。その背景には、日本が直面する深刻な少子高齢化があります。高齢化の進行に伴い、介護を必要とする人々が増え続けており、ケアマネジャーの需要は高まる一方です。
一方で、2018年の介護保険法改正による受験資格の厳格化や、2027年3月末までに居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する原則(※)が設けられるなど、質の高い人材の確保が急務となっています。こうした国の施策も、ケアマネジャーの専門性と社会的役割の重要性を示しています。
また、AI技術の進化により多くの仕事が代替されると懸念される中、ケアマネジャーは利用者一人ひとりの生活や価値観に寄り添い、複雑な人間関係を調整する高いコミュニケーション能力が不可欠です。この人間的な側面はAIでは代替しきれないため、将来的にもケアマネジャーの仕事がなくなる可能性は低いでしょう。
需要が高まる一方で、ケアマネジャーの高齢化や人材不足が課題となっています。この状況が続けば、給与や勤務条件が改善される可能性も期待でき、働きやすい環境が整備されていくでしょう。
(※2024年度の介護報酬改定により、2027年3月末まで猶予期間が設けられています)
スカウトサービス登録はこちらケアマネジャーにまつわるQ&A
ケアマネジャーは国家資格ですか?
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、国家資格ではありません。都道府県が管轄する公的資格です。試験の実施や資格の登録、更新研修などは、各都道府県が行っています。しかし、受験資格として介護福祉士や看護師などの国家資格が求められるため、非常に専門性の高い職種として位置づけられています。
ケアマネジャーは夜勤がありますか?
基本的に夜勤はありません。ケアマネジャーの主な業務は、日中に利用者や関係機関と連携・調整を行う居宅訪問や会議、書類作成です。そのため、勤務時間は日勤が中心となります。ただし、緊急時には時間外の対応が必要になることもあります。施設に勤務するケアマネジャーの場合、施設の状況によっては緊急対応が発生する場合もあるため、まれに夜間の呼び出しや対応が必要になるケースもあります。
ケアマネジャーのシャドーワークとは何ですか?
シャドーワークとは、ケアマネジメント業務を行う上で、居宅介護支援事業所の運営基準では定められていないものの、実質的に発生している業務を指します。具体的には、利用者や家族の個人的な相談対応、通院の付き添い、金銭管理の手伝い、ゴミ出しの援助など、介護保険サービス外のボランティア的な支援です。これらはケアマネジャーの善意や使命感から行われることが多いですが、業務量が増え、負担となることが問題視されています。
ケアマネジャーがやってはいけないことは?
ケアマネジャーは、介護保険法と倫理規定に基づき、以下の行為が禁止されています。
- 不正請求や虚偽の記録
- 特定の事業者への不適切な誘導・勧誘(利益相反)
- 利用者のプライバシーを侵害する行為
- 業務範囲を逸脱した医療行為
これらの行為は、ケアマネジャーの公正性・専門性を損なうため、厳しく禁止されています。
スカウトサービス登録はこちらまとめ
ここまでケアマネジャーの仕事内容から年収、資格取得方法まで詳しく解説してきました。
ケアマネジャーは、高齢化が進む日本社会において、利用者一人ひとりの人生に深く寄り添い、その人らしい生活を支える重要な役割を担っています。
資格取得には専門的な知識と実務経験が必要とされますが、その分、利用者やご家族からの「ありがとう」という感謝の言葉や、社会貢献性の高さからくる大きなやりがいを感じられる仕事です。
今回の記事が、ケアマネジャーの仕事に興味を持つ方、あるいはすでに従事されている方にとって、この仕事の奥深さと可能性を再認識するきっかけとなれば幸いです。
事業所からスカウトがくる!
- スカウト経由で内定率2.3倍!
- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!










